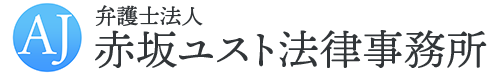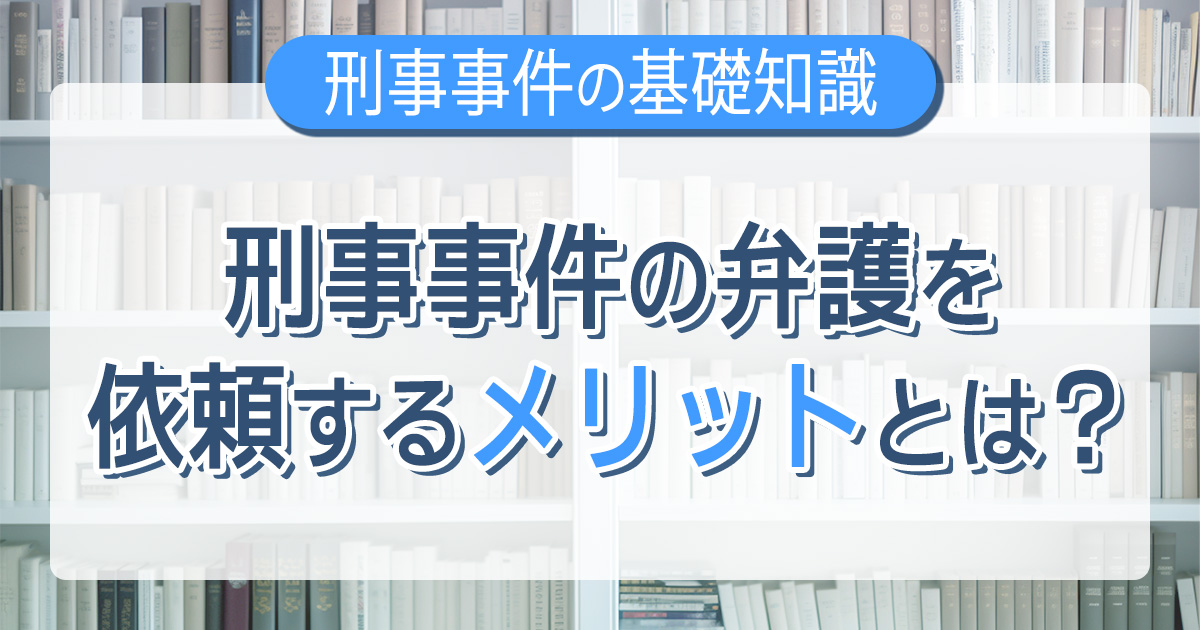刑事事件を犯した場合、処罰がどうなるのか、被疑者の不安は尽きません。そうした場合に、弁護士がどう対応してくれるのかは知りたいところです。そして、刑事事件の弁護を弁護士に依頼するメリットは、重大な関心事となります。
そこで以下では、刑事事件の弁護を弁護士に依頼した場合に、どのようなメリットが考えられるのかなどについて説明します。
報道されずに済む可能性
刑事事件が発覚し、被疑者が逮捕された場合には、ごく軽微な事件を除き、実名報道がされているのが実情です。
実名報道がされれば、被疑者本人やその家族が受ける不利益は大きいものです。
しかし、被疑者の犯した刑事事件が発覚する前に、弁護士が被疑者の自首に同行した場合、捜査機関(警察官や検察官)が被疑者には逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断し、被疑者の逮捕を見送ることも考えられ、そのような事態になれば、事件や実名が報道されずに済む可能性があるといえます。
学校や職場への対応や家族の精神的な支え
以下では、それぞれについて説明します。
学校や職場への対応
被疑者が逮捕され、事件が報道されれば、犯人として氏名が明らかにされてしまうのは、やむを得ないといえます。
しかし、報道されなかった場合、警察が、被疑者が逮捕された事実を学校や職場に知らせることは原則としてありません。それでも、被疑者の身柄拘束が長引くほど、学校や職場に知られないようにすることは非常に困難になります。
そこで、経験豊富な弁護士が責任を持って、学校や職場への対応を行います。
そのため、弁護士は事件の内容に応じて、被疑者が学校や職場に逮捕を知られずに社会復帰できるよう、早期の身柄解放に向けて手を尽くします。
家族の精神的な支え
被疑者が逮捕された場合、その逮捕中(最大72時間)は、家族でも被疑者と面会することができません。
そのため、被疑者の家族は、被疑者の処分がどうなるかを案じ、不安な気持ちに駆られることがあります。そのような場合、弁護士は、被疑者の家族をしっかりサポートし、家族の精神的な支えとなります。
逮捕中も接見が可能
弁護士は、被疑者の逮捕中も、家族とは違い、被疑者と自由に接見(面会)することができます。
弁護士は、被疑者とさまざまな相談ができるほか、家族の状況を伝えたり、被疑者から家族への伝言を仲介したり、着替えや書籍、現金などを差し入れたりすることも可能です。
逮捕・勾留の回避や勾留期間の短縮の可能性
以下では、それぞれについて説明します。
逮捕を回避できる可能性
刑事事件では、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、逮捕して身柄を確保する必要性が高いと考えられます。
したがって、被疑者の逮捕を回避するためには、被疑者に、逮捕の要件である「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」ことが必要です。
そこで、弁護士は、被疑者と面会して、事実関係や身上関係を確認するとともに、家族からも生活状況や保護環境などの事情を聴き取ります。
そして、弁護士は、被疑者が事実関係を認め、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとの心証が得られれば、司法警察員に面談を申し入れ、被疑者の出頭誓約書や適切な身元引受人の身元引受書を提出するなどして、被疑者には逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、在宅捜査が可能である旨を訴え、被疑者を逮捕しないように、また逮捕後であれば被疑者を釈放するように働きかけます。
その結果、司法警察員が弁護士の訴えを受け入れれば、被疑者の逮捕を回避できる可能性があります。
勾留を回避できる可能性
被疑者が逮捕されれば、検察官は最大72時間以内に被疑者の勾留を請求します。
弁護士は、検察官に面談を申し入れ、被疑者の出頭誓約書や身元引受人の身元引受書、弁護士の意見書を提出するなどして、勾留の理由や必要性のないことを訴え、勾留請求をしないように働きかけます。
また、検察官から勾留の請求がなされた場合、担当裁判官に面談を申し入れ、上記の書面を提出するなどして、勾留の理由や必要性のないことを訴え、勾留決定をしないように働きかけます。
そして、勾留決定がなされた場合には、勾留の取り消しを求めて準抗告を申し立てるとともに、準抗告審の裁判官に面談を申し入れ、勾留担当裁判官に提出した書面を踏まえ、勾留の理由や必要性のないことを強く訴え、勾留決定を取り消すように働きかけます。
弁護士がこのような方策を講じた結果、検察官が勾留請求を見送ったり、裁判官が請求を却下したり、準抗告審で勾留決定が取り消されたりすれば、被疑者は釈放され、勾留を回避できる可能性があります。
勾留期間を短縮できる可能性
勾留期間延長決定がなされた場合には、その取り消しまたは変更(たとえば延長期間の短縮)を求めて準抗告を申し立てるとともに、準抗告審の裁判官に面談を申し入れ、勾留期間を延長する理由や必要性のないことを訴え、勾留期間延長決定を取り消すように、あるいは延長期間を短縮するように働きかけます。
その結果、準抗告審で勾留期間延長決定が取り消されたり、変更されたりすれば、勾留期間が短縮される可能性もあります。
取り調べに関するアドバイス
被疑者が逮捕され、捜査機関と対峙して取り調べを受けるとなれば、事実と事実でないことを明確に分けて供述することができず、否定すべきところもあいまいにしてしまい、また本来であれば黙秘権を行使すべきであるのに、黙秘権を行使することができないまま、供述してしまうこともあるかもしれません。
そうした被疑者には、弁護士が、捜査の初期段階から関与すれば、被疑者が被疑事実を認めているか否かにかかわらず、捜査機関から取り調べを受ける際、事前に取り調べに関するアドバイスをすることができ、被疑者の供述が不利に扱われることを防ぐことができます。
- 捜査機関とどのようなやり取りをすればよいのか
- 供述はどのようにすべきか
- 何を話し何を話すべきでないのか
- また黙秘権を行使すべきか
- 黙秘権を行使する部分に関して
- 虚偽の供述をすればどうなるのか など
なお、捜査機関の事件の見通しが誤っていた場合、それに沿った捜査機関の追及によって、被疑者の自白が引き出される危険性があるものの、事前に、取り調べに関する弁護士のアドバイスがあれば、その危険性(ひいては冤罪)を回避することができます。
示談の可能性や民事裁判への対応
以下では、それぞれについて説明します。
示談成立の可能性
刑事事件において、被害者との示談は非常に重要な意味を持ちます。というのも、以下のような重要な判断に大きな影響を与える可能性があるからです。
- 捜査段階で身柄が解放されるかどうか
- 検察官が不起訴処分とするかどうか
- 起訴された場合、略式命令請求で済むか、公判請求されるか
- 起訴後の裁判で、罰金や執行猶予付き判決となるか、それとも実刑か
- 実刑となった場合でも、刑期が軽減されるかどうか
- 保釈が許されるかどうか
上記のように、刑事事件の今後の処分に関わるあらゆる場面で、示談の有無は極めて重要な要素となります。
刑事事件では、被疑者(あるいは起訴後の被告人)が被害者の氏名や住所等を知りうる場合もありますが、そのような場合であっても、被疑者・被告人やその家族が被害者と直接交渉をもつことは、被害者に対する圧力あるいは証拠隠滅行為と受け取られかねないだけに、差し控えるのが望ましいです。
被害者は、犯罪の種類を問わず、精神的に大きく傷ついています。さらに、示談交渉に応じなければならないとなれば、その精神的負担の大きさは計り知れません。
そして、捜査機関は、被疑者・被告人やその家族が被害者の氏名や住所等を知らない場合、被害者のプライバシー保護の観点から、被害者の氏名や住所、連絡先等を被疑者・被告人側に教えることは決してしません。そのため、被害者との折衝や示談交渉などは、法律のプロである弁護士に委ねるべきです。
しかし、弁護士であっても、捜査機関の意向を無視して、被害者と直接折衝したり、示談交渉を行うことはできません。捜査機関は、捜査や公判の進捗状況、被害者の精神状態を踏まえ、被疑者・被告人側に教えないことを条件に、弁護士を信頼して、被害者の承諾が得られた場合に限り、被害者の連絡先等を開示します。
弁護士は、被害者(あるいはその家族)の心情にも配慮しながら示談交渉に臨みますので、誠意をもって被害者と話し合うことで、示談成立の可能性が高まります。
民事裁判の代理人としての対応
刑事事件によっては、損害賠償請求あるいは慰謝料請求などの民事的な問題に発展することもあります。
そのような場合は、刑事事件に関わるため、当事者同士での解決は難しく、そこは弁護士に頼るべきです。
民事裁判となったとしても、弁護士であれば、被疑者(あるいは起訴後の被告人)の代理人として対応し、和解を含む早期の解決が望めますので、刑事事件においても、被疑者・被告人に有利な事情として考慮されることが期待できます。
不起訴処分の可能性
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと決める処分のことをいいます。
捜査段階では、捜査機関手持ちの捜査資料は開示されませんので、弁護士は、被疑者との接見を通じて得た情報をもとに、犯罪の成否を含む事実関係を把握せざるを得ません。
刑事事件の起訴・不起訴の処分は、犯罪の罪質・態様・結果、被害回復、慰謝の措置、被害感情や前科前歴の有無など、さまざまな事情によって決まります。
特に不起訴処分のうち、起訴猶予は、検察官が、犯罪の嫌疑がある場合において、被疑者の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする処分になります。
不起訴処分で事件が終結すれば、被疑者の早期の社会復帰が可能になるうえ、被疑者が受ける社会的な不利益を最小限にとどめることができます。
弁護士は、被害者と示談するのはもちろん、家族や身元引受人による社会復帰後の更生環境を整え、雇用先を確保するなどして、被疑者を社会内で更生させるのが望ましい旨を捜査機関や裁判官に訴えて、被疑者が逮捕・勾留段階で身柄拘束から解放されれば、検察官による不起訴処分の可能性が高まります。
自首する際の同行
自首は、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることです。
犯罪を犯した者であれば、自首後の逮捕は覚悟しているとはいえ、捜査機関に一人で出頭するには勇気がいるものです。そのうえ、自首後の取り調べへの対応や、残される家族のことを思うと、自首をためらってしまうこともあります。
しかし、自首する前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることで、犯行によって得た金品や犯罪を裏づける証拠物(薬物など)を持参し、弁護士に同行してもらいながら捜査機関へ出頭することが可能になります。
自首を受理した司法警察員は、自首した被疑者に犯罪事実を確認するとともに、弁護士から逃亡や証拠隠滅のおそれがない旨の根拠を示す説明があり、被疑者の身上や勤務状況、今後の身元引受関係の確認ができた場合には、事件の罪質や内容によるとはいえ、逮捕を見合わせることも考えられます。仮に逮捕されたとしても、自首した場合には、勾留を回避できる可能性もあります。
また、検察官は、自首は反省悔悟と更生の意欲の表れと評価できるため、同種の前科前歴があるなど、不起訴処分を不相当とする事情がない限り、起訴猶予の不起訴処分にしたり、起訴するにしても、罰金の選択刑があれば、略式命令請求にとどめたりします。
さらに、犯人の申告が法律上の自首にあたる場合、裁判所は、その刑を減軽したり、あるいは刑の減軽をしないとしても、被告人の反省の気持ちや更生に対する意欲の表れとして、有利な情状として一定の評価をするのが一般的になっています。
刑罰が軽減される可能性
弁護士は、弁護活動を通じて、被害者に対し誠意ある謝罪をし、その結果として示談の成立や、慰謝の措置を講じることができれば、不起訴処分で終わったり、仮に起訴されたとしても、事件によっては略式命令請求にとどまる可能性が考えられます。
また、公判請求されるのはやむを得ない場合であっても、弁護士が、示談成立、慰謝の措置、被告人の反省悔悟の気持ちや更生の意欲、社会復帰後の保護環境など、被告人に有利な情状を立証することにより、執行猶予付きの判決が得られたり、仮に実刑が避けられないとしても、刑期が軽減される可能性があります。
まとめ
刑事事件を犯した被疑者(その家族を含みます)が、その弁護を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのかを説明しましたが、ご理解いただけたでしょうか。
被疑者本人やその家族の方が、刑事事件のことで悩まれている場合、どの段階で弁護士に相談するのが望ましいのかや刑事事件の弁護を弁護士に依頼するメリットなどを知りたい場合には、ぜひ一度刑事事件に精通している弁護士にご相談ください。