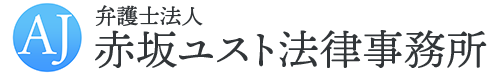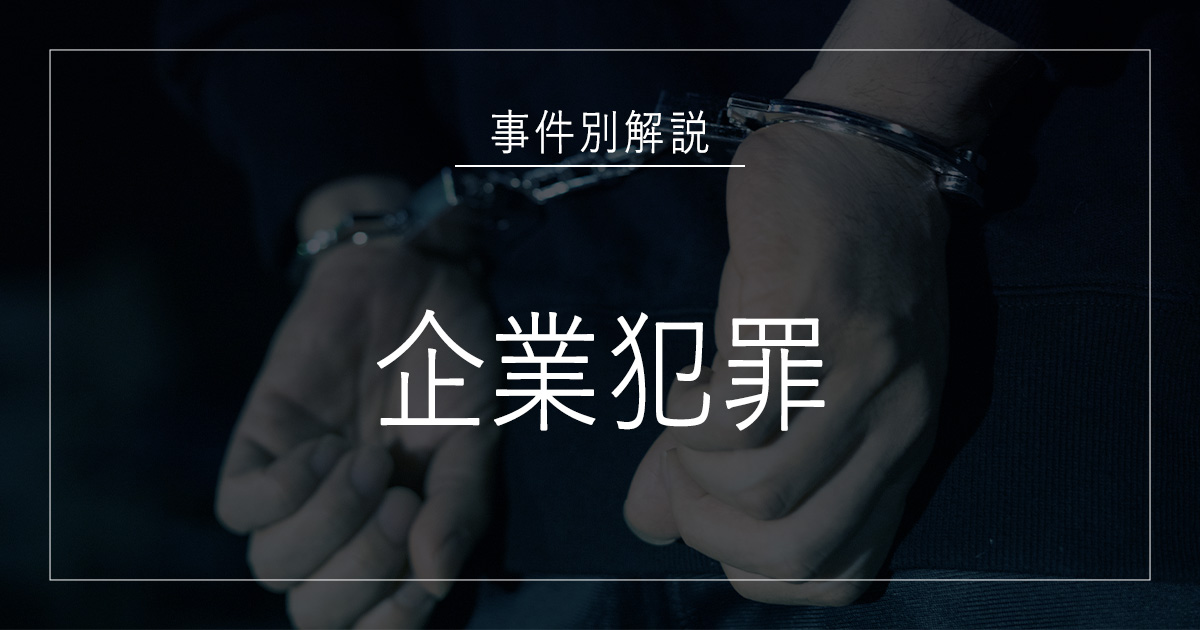企業犯罪で逮捕された場合、会社からどのような処分を受けるのか、また、その後にどんな刑事処分が下されるのか、不安に感じる方は少なくありません。
さらに、被疑者のご家族も、検察官の判断や裁判所の結論が少しでも本人にとって有利になることを願い、経験豊富な弁護士に相談したいと考えるケースが多く見られます。
この記事では、主な企業犯罪の内容、主な企業犯罪の罰則、よくある事例などについて解説します。
企業犯罪とは?
企業犯罪とは、企業の経済活動に関わる中で行われる不正や違法行為のことを指します。
企業犯罪といっても種類はさまざまですが、この記事では代表的なものとして、以下の罪を取り上げます。
- 会社犯罪の代表例
特別背任罪、違法配当罪など - 経済犯罪の代表例
不当な取引制限の罪(いわゆるカルテルや談合など) - 証券犯罪の代表例
相場操縦罪、インサイダー取引罪
なお、本文中では、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」を「独禁法」、「金融商品取引法」を「金商法」と略称します。
主な企業犯罪の内容
以下、主な企業犯罪の内容について説明します。
特別背任罪
特別背任罪は、取締役など会社で重要な役割を担う者が、自分や第三者の利益を図り、あるいは、会社に損害を加えようとして、自らの任務に違背し、会社に財産上の損害を生じさせたときに成立します(会社法960条)。
たとえば、銀行の融資担当者が、融資先会社の代表取締役と共謀して、十分な担保も取らずに貸し付けたため、融資金を回収できず、銀行に損害が発生した場合に、担当者の融資判断が著しく不合理であって、適切な債権保全義務に違反していれば、融資担当者には特別背任罪が成立することになります。不正融資あるいは不良貸付といわれるものです。
ただし、犯罪の成立要件との関係で注意が必要です。
客観的な損害が生じただけで、ただちに特別背任罪が成立するわけではなく、特別背任罪の成立は、融資担当者が、自分(の身内)や融資先の利益を図ったり、銀行に損害を加える目的があった場合に限定されるからです。いわゆる図利加害目的が必要なのです。
特別背任罪では、たとえ勤務先や会社経営者に多額の財産的損害を与えた場合でも、それが会社のために行動した結果であれば、犯罪の成立に必要な「図利加害目的」がなかったことになります。
特別背任罪では、金融機関による不正融資や企業経営者による企業の私物化・放漫経営などが問題になっています。
なお、行為の主体は、発起人や取締役だけでなく、監査役・支配人のほか、特定の業務を行う部課長クラスの人も含まれます(会社法960条1項7号など)。
違法配当罪
違法配当罪は、法令・定款の規定に違反して、剰余金(利益・利息など)を配当したときに成立します(会社法963条5項2号)。
たとえば、配当可能な利益がないのに、貸借対照表や損益計算書を改ざんするなど、不当な会計処理により架空利益を計上するなどして株主に配当する場合、分配可能な剰余金があっても、定時株主総会の承認決議を経ていない場合、株主総会の承認決議があったとしても、およそ分配可能な剰余金がなかったり、会計上許された限度を超えて配当する場合には、いずれも違法配当罪が成立します。
違法配当罪は、会社の財務状況について出資者を欺くだけでなく、虚偽内容の有価証券報告書を提出することで、市場の信頼も低下させる行為です。
不当な取引制限の罪
不当な取引制限の罪は、事業者が、他の事業者と共同して、相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限したときに成立します(独禁法89条1項1号後段)。
不当な取引制限として代表的なのは、業者間で連絡を取り合い、商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決めるカルテル、公共工事や物品調達に関する入札に際し、事前に受注業者や受注金額などを決めてしまう入札談合などといった行為です。
たとえば、ある市が発注する特定の分野の公共工事に関して、入札参加資格のある業者が集まり、共存共栄を図るために、年間を通して各工事の受注者をあらかじめ取り決めた場合、取り決めに参加した業者間では、受注予定の業者が確実に工事を落札できるようにするために、互いに入札価格を教え合い、受注予定の業者が最も低い入札価格にするなどといった受注調整が行われることになります。
このような場合、市の特定の分野の公共工事に関しては、各業者が品質の良いものをより安価で提供・供給するための努力をする必要がなくなるため、自由な競争が成り立たなくなることから、不当な取引制限の罪が成立するのです。
なお、不当な取引制限の罪に関しては、専門機関である公正取引委員会が刑事告発に向けて調査を行い、その調査結果に基づき、刑事処罰を求めて告発をしなければ、検察官は起訴できないという仕組みになっています。
相場操縦の罪
相場操縦の罪は、相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させ、金商法が禁止する行為をしたときに成立します(金商法159条)。
たとえば、買い注文や売り注文の出し方を操作することによって、売買が頻繁に行われている銘柄であるものと他の投資家に誤解させ、注文を誘引して株価を吊り上げるなどといった行為をすれば、相場操縦の罪が成立します。
相場操縦は、市場における公正な価格形成を歪め、投資家に不測の損害を与える行為です。
相場操縦の取引に当たる主な行為には、仮装売買、馴れ合い売買、変動操作取引、違法な安定操作取引があります。
インサイダー取引の罪
インサイダー取引の罪は、投資家の判断に重要な影響を及ぼす情報を知りうる上場会社の役員等が、そのような未公表の重要な情報を知りながら、株式などの売買を行うことによって成立します(金商法166条、167条)。
たとえば、会社の幹部が、株価の上昇原因となる自社の合併情報を持っている場合、親族に購入をすすめ、親族にその名義で自社の株式を取得させれば、インサイダー取引の罪が成立します。
上場会社の役員等は、職務を通じて、一般の投資家が知りえない有益な情報を入手することができます。そのような一部の人だけが、その情報を利用して、抜け駆け的に株式取引などを行って利益を得ようとすれば、証券市場や証券取引の公平性・信頼性は損なわれてしまいます。
主な企業犯罪の罰則
主な企業犯罪の罰則は、以下の罪名・罰条に対応するとおりです。
なお、罰則に記載されている懲役は「拘禁刑」と表記されるようになります。この変更は、令和7年(2025年)6月1日(改正刑法施行日)から適用されます。
| 罪名 | 罰条 | 罰則 |
| 特別背任 | 会社法960条 | 10年以下の懲役(拘禁刑)もしくは1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役(拘禁刑)および1,000万円以下の罰金 |
| 違法配当 | 会社法963条5項2号 | 5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、または5年以下の懲役(拘禁刑)および500万円以下の罰金 |
| 不当な取引制限 | 独禁法89条1項1号後段 | 5年以下の懲役(拘禁刑)または500万円以下の罰金 |
| 相場操縦 | 金商法197条1項5号 | 10年以下の懲役(拘禁刑)もしくは1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役(拘禁刑)および1,000万円以下の罰金 |
| インサイダー取引 | 金商法197条の2第13号 | 5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、または5年以下の懲役(拘禁刑)および500万円以下の罰金 |
| 罪名 | 特別背任 |
| 罰条 | 会社法960条 |
| 罰則 | 10年以下の懲役(拘禁刑)もしくは1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役(拘禁刑)および1,000万円以下の罰金 |
| 罪名 | 違法配当 |
| 罰条 | 会社法963条5項2号 |
| 罰則 | 5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、または5年以下の懲役(拘禁刑)および500万円以下の罰金 |
| 罪名 | 不当な取引制限 |
| 罰条 | 独禁法89条1項1号後段 |
| 罰則 | 5年以下の懲役(拘禁刑)または500万円以下の罰金 |
| 罪名 | 相場操縦 |
| 罰条 | 金商法197条1項5号 |
| 罰則 | 10年以下の懲役(拘禁刑)もしくは1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役(拘禁刑)および1,000万円以下の罰金 |
| 罪名 | インサイダー取引 |
| 罰条 | 金商法197条の2第13号 |
| 罰則 | 5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、または5年以下の懲役(拘禁刑)および500万円以下の罰金 |
よくある事例
主な企業犯罪でよくある事例は、以下のとおりです。
粉飾決算のケース
粉飾決算とは、一般的に、会計手法を用いて虚偽の財務諸表を作成し、企業の経営成績および財政成績を実際よりも良好に、または悪く表示することをいうと解されています。
なお、経営成績や財政成績を良好に表示する場合を狭義の粉飾決算といい、悪く表示する場合を逆粉飾という場合もあります。
売り上げの架空計上
自社のグループ内に子会社がある場合に、子会社と取引があったかのように取引を捏造して、売り上げを架空計上し、利益を意図的に増やすことは、粉飾決算の手口といえます。
在庫の架空計上
在庫は、会計上、棚卸資産として扱われ、貸借対照表において資産に計上されます。本来存在しない在庫を架空計上し、棚卸資産があるように見せかけ、利益を意図的に水増しすることは、粉飾決算の手口といえます。
相場操縦のケース
相場操縦について、典型的な例を見てみましょう。
仮装売買
ある特定の株式の売買が頻繁に行われているものと他の投資家を誤解させ、他の投資家の取引を誘引することを目的として、同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の株式について、同じ時期に同じ価格で売り買いの注文を発注して売買することは、仮装売買として禁止されている行為です。
馴れ合い売買
ある特定の株式の売買が頻繁に行われているものと他の投資家を誤解させ、他の投資家の取引を誘引することを目的として、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の株式について、ある者の売り付け(買い付け)と同じ時期に同じ価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、馴れ合い売買として禁止されている行為です。
インサイダー取引のケース
上場会社の社員が、投資判断に重要な影響を及ぼす情報を知りえた場合に、自らの名義で株式の売買等を行えば、すぐに発覚してしまうおそれがあるため、老後の資金を心配している自分の親に未公表の情報を伝え、親がその情報をもとに株式を購入した場合には、インサイダー取引に当たり、社員は会社関係者として、その親は情報受領者として処罰されます。
インサイダー取引の規制は、未公表の重要事実を知る者による不公正な取引を防止するために設けられています。この規制は、会社関係者だけではなく、情報受領者も対象になります。
なお、情報受領者とは、会社関係者から未公表の重要事実を伝えられた者のことをいいます。
まとめ
企業犯罪で逮捕された場合、不安や疑問が募ることと思います。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
企業犯罪は、企業の経済活動に関わるだけに専門的な知識が求められます。また、企業側とのやり取りも含めて、法律の専門家である弁護士に相談するのが適切です。
弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。企業犯罪でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。