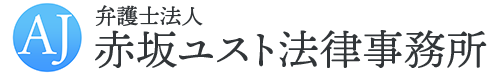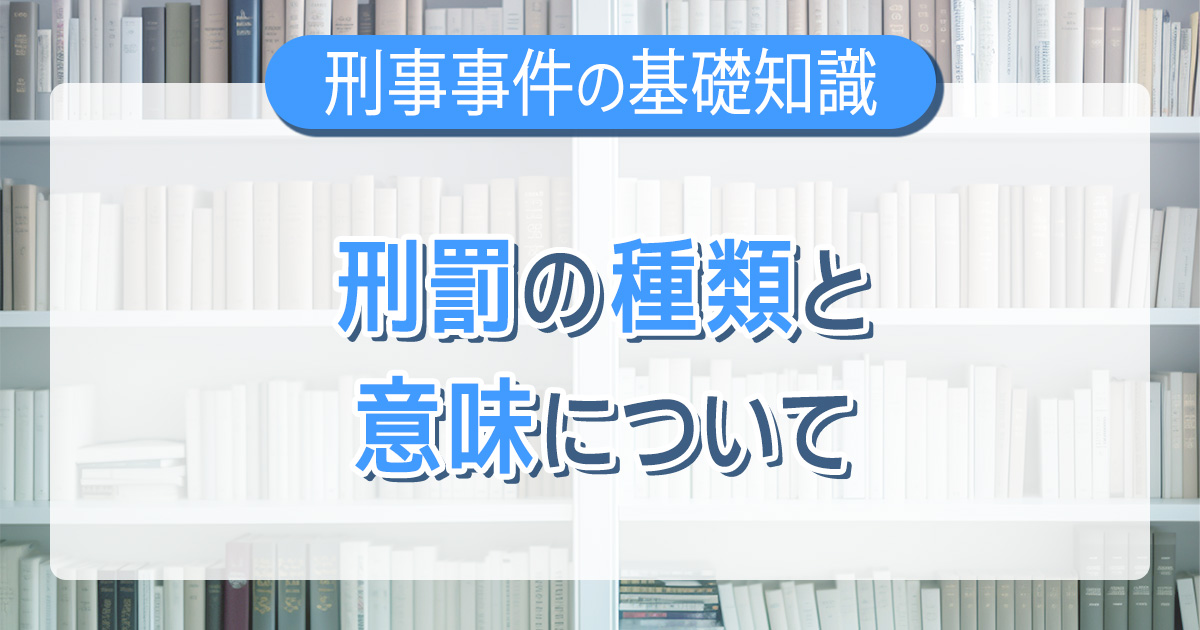刑事裁判で有罪となる場合、同時に刑罰が言い渡されます。刑罰の内容は刑法に規定されていますが、どのような種類があり、どのような意味なのでしょうか。
そこで以下では、刑罰の種類と、それぞれの刑罰がどのような意味なのかについて、2025年6月1日からの改正も踏まえて説明します。
刑罰の種類
2025年4月現在、日本における刑罰には次の種類があります。
- 主刑
- 死刑
- 懲役
- 禁錮
- 罰金
- 拘留
- 科料
- 付加刑
- 没収
この内容は2025年6月1日から施行される新しい刑法の制度において、懲役と禁錮が拘禁刑に変更されるので注意しましょう。
- 主刑
- 死刑
- 拘禁刑
- 罰金
- 拘留
- 科料
- 付加刑
- 没収
死刑とは
死刑とは、生命を奪う刑です。
死刑は刑務所で絞首刑として執行され、執行までの間は刑務所に拘束されます。
- 殺人罪
- 強盗殺人罪
- 内乱罪
- 外患誘致罪
- 現住建造物等放火罪 など
懲役とは
懲役とは、身柄を拘束して自由を奪うもので、刑務所で所定の作業につかせる刑罰です。
懲役には有期懲役と無期懲役の2種類があり、有期懲役の期間は原則として1か月~20年とされています。
- 殺人罪
- 窃盗罪
- 詐欺罪
- 撮影罪
- 児童買春
- 名誉毀損罪
- 覚せい剤取締法違反
- 酒気帯び運転 など
禁錮とは
禁錮とは、身柄を拘束して自由を奪うもので、刑務所に収容する刑罰です。
懲役と異なり刑務所での作業につかせられないという違いがあります。過失による犯罪で言い渡されることが多いとされます。
禁錮には有期禁錮と無期禁錮の2種類があり、有期禁錮の期間は原則として1か月~20年とされています。
- 過失運転致死傷罪
- 業務上失火罪
- 業務上過失致死傷
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪 など
拘禁刑
拘禁刑とは、身柄を拘束して自由を奪う刑罰で、刑務所に収容し、必要な作業を行わせたり、必要な指導を行う刑罰です。
従来の禁錮制度においても受刑者は作業を行うことができ、実際に禁錮が言い渡されても作業を志願する人が多く、懲役と禁錮の違いはあまり感じられなくなっていました。また、懲役では作業をさせるために十分な更生プログラムを行えないという不都合もありました。そこで新たに拘禁刑を規定して、再犯防止に重視したものになっています。
罰金とは
罰金とは、金銭を奪う刑罰です。原則として1万円以上で、上限は各法令で定められています。
罰金の納付ができない場合は、罰金を納める代わりに労役場に留置され、所定の作業に従事させられます。身柄拘束ができない法人にも科すことができます。
- 住居侵入等
- 過失傷害
- 道路交通法違反
- 労働基準法違反
- 独占禁止法違反 など
拘留
拘留とは、身柄を拘束して自由を奪うもので、通常は刑務所ではなく、拘置所に収容される刑罰です。
懲役や禁錮との違いは期間が1日以上30日未満であることです。
- 公然わいせつ罪
- 侮辱罪
- 暴行罪
- 軽犯罪法違反 など
刑事事件において、起訴前・起訴後に行われる身柄拘束である「勾留」とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。
科料
科料とは、金銭を奪う刑罰です。
罰金との違いは金額で、科料では1,000円以上1万円未満です。科料の支払いができない場合も労役場留置となります。
- 公然わいせつ罪
- 侮辱罪
- 暴行罪
- 軽犯罪法違反
- 道路交通法違反 など
行政上の義務違反として科される制裁である「過料」と区別するため、科料は「とがりょう」とも呼ばれることがあります。
没収
没収とは、犯罪に関係のある物の所有権を奪う刑罰です。犯罪に使ったものや犯罪によって得たものについて所有権を奪うことで、再犯を防止します。
| 没収の対象になるもの | 具体例 |
| 犯罪行為の一部を構成しているもの | 文書偽造罪の場合の偽造された文書 |
| 犯罪のために使った・使おうとしたもの | 殺人罪の場合の凶器 |
| 犯罪によって出来上がったものや得た報酬 | 通貨偽造罪の場合の偽造通貨賭博で得たお金 |
| 犯罪によって取得した物の対価として得たもの | 盗んだ物を売却して得た利益 |
また、すでに金銭を使ってしまって無いような場合には、不正に得た金品相当額を納付させる「追徴」も付加刑として挙げられます。
執行猶予とは
執行猶予とは、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金刑を言い渡されたときに、刑の執行を一定期間猶予するものです。執行猶予の期間は1年~5年で、その間に執行猶予が取り消されなければ、刑の言い渡しは効力を失います。
執行猶予がされず懲役・禁錮として刑務所に収監される場合を「実刑」といいます。
まとめ
刑罰の種類と意味について解説しました。2025年4月時点では6つの主刑と付加刑があり、2025年6月1日からは懲役と禁錮が統合して拘禁刑となります。
犯罪を犯してしまった場合には起訴されないようにする、起訴された場合にはより軽い罪や執行猶予で済むように適切な対応が必要です。出来るだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。