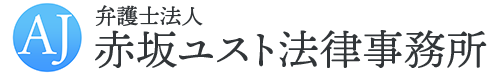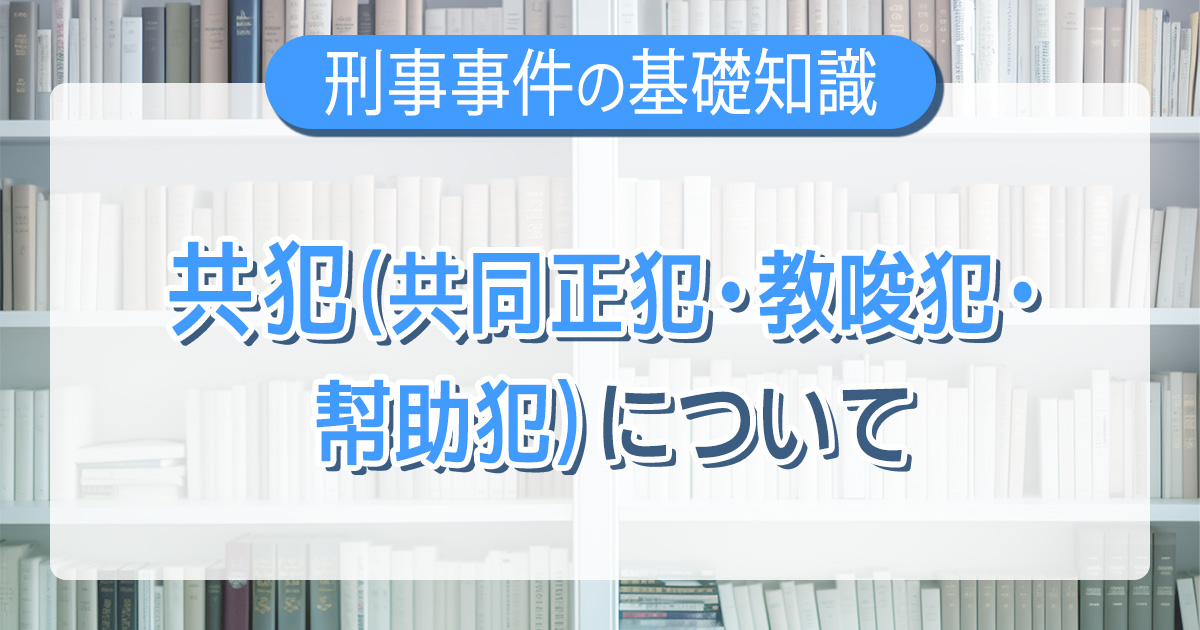犯罪は、1人ではなく複数の人が関わって行われることがあります。こうした複数人が関与して行われる犯罪を「共犯」といい、共犯は共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つに分けられます。
そこで以下では、共犯の内容や、罪に問われた場合にどのように扱われるのかについて説明します。
共犯とその種類
複数の者が犯罪に関与している場合、それは共犯です。
必要的共犯と任意的共犯
共犯は、まず犯罪自体が複数の者によるものである必要的共犯と、単独の者による犯罪を複数の者で行う任意的共犯に分類されます。
| 種類 | 例 |
| 必要的共犯 | 重婚罪(配偶者のある者とその相手が必要)、賄賂罪(賄賂を与える人と受け取る人が必要)、わいせつ物頒布罪(わいせつ物を頒布する人と受け取る人が必要) |
| 任意的共犯 | 窃盗罪、傷害罪、詐欺罪など |
任意的共犯の3種類(共同正犯・教唆犯・幇助犯)
その関与の程度に応じて、共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つに分けられます。
| 共犯の種類 | 内容 | 処罰 |
| 共同正犯 | 共同して犯罪を実行すること | 正犯として処罰 |
| 教唆犯 | 犯罪をそそのかすこと | 正犯として処罰 |
| 幇助犯 | 犯罪を手助けすること | 従犯として処罰 |
なお、正犯とは自ら犯罪を行う者、従犯とは正犯を手助けする者を指します。
共同正犯(刑法第60条)
共同して犯罪を実行することを共同正犯といいます。
例えば、1人が暴行して怪我をさせた場合、傷害罪が成立しますが、複数人で暴行を加えて怪我をさせた場合、暴行に参加した全員が傷害罪の共同正犯となります。
なお、実行行為を行っていない場合でも、共謀に加わったことをもって、共同正犯として扱われることもあります(共謀共同正犯)。暴力団による刑事事件で、実際に実行していない幹部に刑事責任を負わせるようなケースで問題になります。
共同正犯として扱われる場合、全員が1人で犯罪を行った場合と同様に正犯として処罰されます。
教唆犯(刑法第61条)
人をそそのかして犯罪を行わせるのが教唆犯です。
例えば、AがBに対して「Cを殴ってこい」とそそのかし、BがCを殴って怪我を負わせるようなケースで、Bには傷害罪が、Aには傷害罪の教唆犯が成立します。もっとも、教唆犯が成立するためには、そそのかされた結果、正犯が犯罪を実行することが必要です。そのため、他人が犯罪を実行しなかった場合や、そそのかした行為とは無関係に正犯が犯罪を実行した場合、教唆犯は成立しません。
実行行為を行っていない点で教唆犯と共謀共同正犯は共通します。その違いは犯罪の重要な役割を担っているか、そそのかしたに過ぎないかです。
教唆犯は正犯として処罰されますが、正犯よりも刑が軽くなる傾向があります。そのため、共謀共同正犯として刑事責任を追及されている場合には、教唆犯に過ぎないと主張し、刑を軽くしてもらうように活動する必要があります。
幇助犯(刑法第62条)
犯罪を手助けするのが幇助犯です。
例えば、Aが住居侵入をするために、BがAに道具を貸したケースでは、Aには住居侵入罪が、Bには住居侵入罪の幇助犯が成立します。凶器の準備や逃走の手助けなど、物理的なものはもちろん、心理的に励ますなど精神的なものであっても成立します。本人は手助けのつもりでも、犯罪の一部を実行しているので幇助犯ではなく共同正犯です。例えば、本人は手助けのつもりでも、特殊詐欺の受け子(現金を受け取る役目)は実行行為の一部なので、幇助犯ではなく共同正犯となります。
幇助犯は従犯とされ、従犯は正犯の刑を減軽する(=半分にする)ことがあります。
共犯事件になりやすい犯罪
犯罪のうち共犯になりやすい犯罪として、詐欺罪・強盗罪・恐喝罪が挙げられます。
詐欺罪
詐欺罪では、特に特殊詐欺において、前述の受け子や出し子(奪ったキャッシュカードで現金を引き出す役割)などのほか、さまざまな役割を持った人々が関与し、共犯となりやすいことが知られています。
強盗罪・恐喝罪
強盗罪や恐喝罪は、多数の人が計画して行うことが多く、共犯になりやすいことが知られています。
共犯事件における3つの特徴
共犯事件には、次の3つの特徴があります。
- 逮捕・勾留される可能性が高くなる
- 勾留が長期化することがある
- 接見禁止処分が下される可能性が高い
逮捕・勾留される可能性が高くなる
逮捕・勾留は罪証隠滅・逃亡を防ぐためにされますが、共犯事件では共犯者に証拠隠滅される可能性が高くなるため、逮捕・勾留される可能性が高まります。
勾留が長期化する
起訴前の勾留は20日、起訴後には2か月で、必要に応じて1か月ごとに更新されます。共犯事件では罪証隠滅・逃亡を防ぐ必要があるので、勾留が長期化し保釈の許可も下りない可能性が高いです。
接見禁止処分が下される可能性が高い
共犯事件では、まだ逮捕されていない共犯者や事件の関係者が接見に来て、証拠隠滅や口裏合わせなどを行うおそれがあり、接見禁止処分が下される可能性が高いです。
まとめ
本記事では、共犯について解説しました。
共犯は、関わり方によって共同正犯、教唆犯、幇助犯に分けられます。共犯事件では、逮捕や勾留といった身柄拘束の可能性が高く、拘束が長引いたり、接見禁止処分が出されることもあるため、不利な状況に陥りやすいのが特徴です。さらに、どの種類に認定されるかによって刑の重さが変わるため、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。