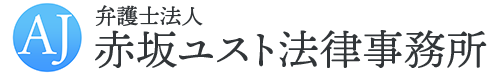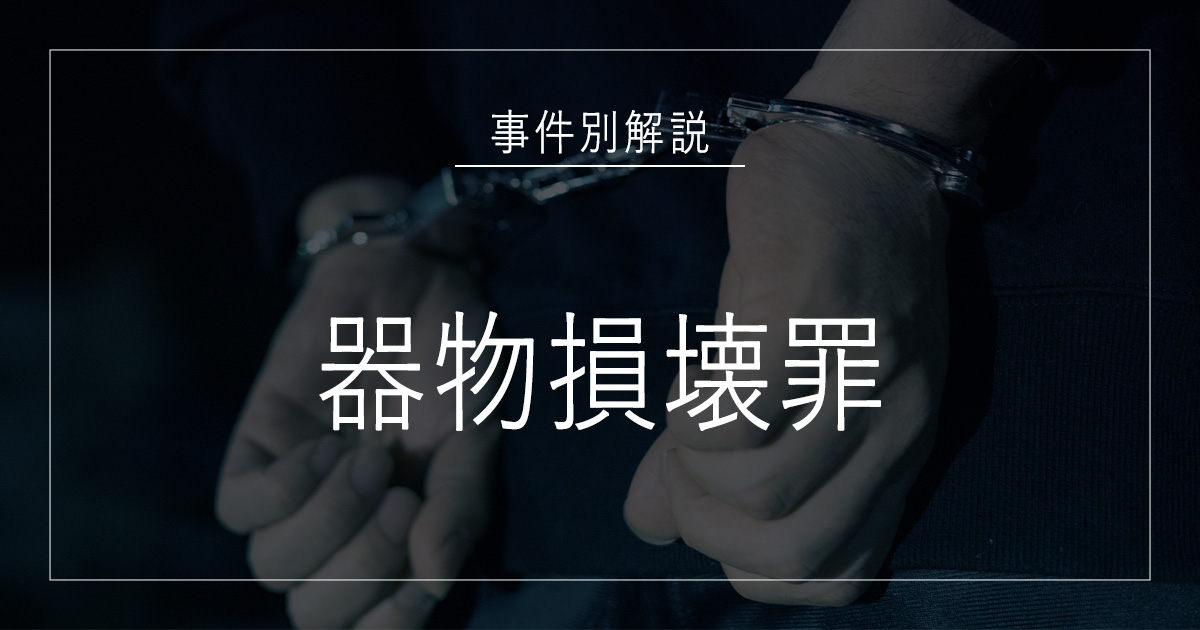器物損壊罪で逮捕された場合、今後の手続きがどう進むのか、身柄拘束がどの程度続くのか、また起訴・不起訴の見通しがどうなるのかなど、不安を抱く方も多いでしょう。
また、逮捕された被疑者の家族も、刑事事件に精通した弁護士に依頼したいと考えることが多いでしょう。
以下では、器物損壊罪の内容、器物損壊罪の成否、器物損壊罪を含む毀棄および隠匿の罪の身柄状況、器物損壊罪の逮捕後の流れ、器物損壊罪の終局処理状況、器物損壊罪の量刑傾向、よくある事例などについて説明します。
なお、以下に示す刑法の条文は、条文番号のみを掲げています。
器物損壊罪の内容
以下で、器物損壊罪の内容について見てみましょう。
犯罪の成立
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、または傷害することによって成立します(261条)。
客体
客体は、258条〜260条に規定されるもの以外の他人の物です。
「他人」とは私人に限られず、共有物件は共有者相互に他人の物と扱われます。
一方、無主物は他人の物には該当しません。
自己の物であっても、差押えを受けている場合や、物権を設定している場合、賃貸中である場合、または配偶者居住権が設定されている場合には、器物損壊罪の客体となります(262条)。
客体となる「物」とは、財産権の対象となるあらゆる物件を指します。
ただし、器物損壊罪の客体については、刑法258条〜260条に規定されている対象が法文上除外されているため、それらの物は含まれません。
具体的には、公務所で使用する文書・電磁的記録(258条)、権利や義務に関する他人の文書・電磁的記録(259条)、そして他人の建造物や艦船(260条)は器物損壊罪の客体から外れます。
したがって、これら以外の「他人の物」が器物損壊罪の対象になります。
器物損壊罪の客体となる具体例としては、次のようなものがあります。
- 建造物を除く土地やその他の不動産
- 艦船を除く航空機
- 汽車・電車・自動車などの乗物
- 刑法258条・259条に規定される文書等を除いた各種の物品
- 動物・植物などの生物
このように、法律上除外される特定の物を除き、多くの物が器物損壊罪の客体となり得ます。
行為
行為は、損壊または傷害です。
「損壊」とは、物質的に毀損するだけでなく、その物の効用を害する行為を指します。
したがって、判例上、営業用の食器に放尿すること、政党の演説会告知用ポスターに「殺人者」「人殺し」などと印字されたシールを貼付する行為などは、物の本来の効用を失わせるものとして、「損壊」にあたるとされています。
「傷害」とは、動物について用いられる用語で、殺傷することのほか、判例上、他人の飼育する魚を養魚池外に流出させるような行為も含まれるとされています。
刑罰
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金もしくは科料(1,000円以上1万円未満)です。
なお、器物損壊罪は、親告罪ですので(264条)、告訴がなければ処罰されることはありません。
器物損壊罪の成否
器物損壊罪が成立するためには、客体が他人に属することに加え、損壊や傷害の行為によって客体を物質的に毀損し、または効用を害するとの認識を有している必要があると解されています。
したがって、他人の物を損壊する認識を欠く場合、すなわち故意がない場合には、器物損壊罪は成立しません。
また、器物損壊罪には未遂犯および過失犯を処罰する規定がないため、未遂および過失による行為は処罰されません。
器物損壊罪を含む毀棄および隠匿の罪の身柄状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年における検察庁既済事件の身柄状況(毀棄・隠匿の罪)は、下記のとおりです(同年報「41 罪名別・既済となった事件の被疑者の逮捕および逮捕後の措置別人員」参照)。
| 罪名 | 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 | 警察等で逮捕後釈放 | 警察等で逮捕・身 柄付送致(B) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率(%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率(%) | |
| 毀棄隠匿 | 7,634 | 4,768 | 329 | 2,534 | 3 | 33.2 | 2,017 | 253 | 89.5 |
| 罪名 | 毀棄隠匿 | |
| 逮捕関係 | 総数(A) | 7,634 |
| 逮捕されない者 | 4,768 | |
| 警察等で逮捕後釈放 | 329 | |
| 警察等で逮捕・身 柄付送致(B) | 2,534 | |
| 検察庁で逮捕(C) | 3 | |
| 身柄率(%) | 33.2 | |
| 勾留関係 | 認容(D) | 2,017 |
| 却下(E) | 253 | |
| 勾留請求率(%) | 89.5 | |
なお、身柄状況については、器物損壊罪単独の統計が存在しないため、刑法第40章(毀棄および隠匿の罪)全体の数字を用いています。
また、同年報によれば、令和6年の検察庁終局処理人員は毀棄・隠匿の罪全体で8,456人、そのうち器物損壊罪が7,186人(約85%)を占めています(同年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
この割合から、器物損壊罪の身柄率および勾留請求率も、上記の数値と大差ないものと推計できます。
身柄率は(B+C)÷Aで、勾留請求率は(D+E)÷(B+C)でそれぞれ求めます。
上記の数字の推計から、器物損壊罪を犯した者のうち、約4割弱(数字上は37.5%)の者が逮捕されているものの、約6割強(数字上は62.5%)の者が逮捕されていないこと、また、逮捕された者のうち、約3割(数字上は29.6%)の者が勾留されていないことになります。
器物損壊罪の態様はさまざまで、次のような行為が代表例として挙げられます。
- 自動車・バイク・自転車のタイヤをパンクさせる行為
- 自動車の車体に傷を付けたり、塗料を塗布したりする行為
- 自動車やバイクなどに放火したものの、公共の危険が生じなかったケース
- コインランドリーの両替機や自動販売機を壊す行為
このように悪質性が高い事案では逮捕が避けられませんが、単なるトラブルから他人の物を損壊した場合には、被害額が高額であったり、前科や常習性が認められたりするケースを除き、通常は逮捕に至らないことが多いと考えられます。
器物損壊罪の逮捕後の流れ
器物損壊罪で逮捕された場合、一般的に、被疑者は逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。
検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に、長期の身体拘束を求める勾留請求を裁判官に行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けると、被疑者に対して勾留質問を行い、その当否を審査します。
罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかに該当し、捜査のために身柄拘束が必要と判断される場合に勾留が認められます。
勾留期間は原則10日間ですが、悪質性や常習性のない一般的な器物損壊事件では、さらに10日間の勾留延長が認められるケースは多くありません。
したがって、多くの場合、当初の勾留期間中に起訴・不起訴の判断が下されます。
器物損壊罪の終局処理状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年における器物損壊罪の検察庁終局処理人員は、下記のとおりです。
| 罪名 | 総数 | 起訴 (起訴率) | 公判請求 (起訴で占める率) | 略式請求 (起訴で占める率) | 不起訴 (不起訴率) | 起訴猶予 (不起訴で占める率) | その他 (不起訴で占める率) |
| 器物損壊 | 7,186 | 1,391 (23.6%) | 525 (37.7%) | 866 (62.3%) | 4,493 (76.4%) | 1,044 (23.2%) | 3,449 (76.8%) |
| 罪名 | 器物損壊 |
| 総数 | 7,186 |
| 起訴 (起訴率) | 1,391 (23.6%) |
| 公判請求 (起訴で占める率) | 525 (37.7%) |
| 略式請求 (起訴で占める率) | 866 (62.3%) |
| 不起訴 (不起訴率) | 4,493 (76.4%) |
| 起訴猶予 (不起訴で占める率) | 1,044 (23.2%) |
| その他 (不起訴で占める率) | 3,449 (76.8%) |
起訴率は、「起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100 により算出される百分比のことです。
不起訴率も同様に、「不起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100 で算出されます。
器物損壊罪の量刑傾向
令和6年版犯罪白書(令和5年統計)によれば、地方裁判所における毀棄・隠匿の罪の科刑状況は、懲役刑の実刑が33.3%、執行猶予付き判決が66.7%となっています(同白書「資料2-3」および「2-3-3-1表」参照)。
また、2023年検察統計年報(令和5年統計)によれば、令和5年の器物損壊罪は、起訴総数1,343人のうち公判請求が516人、略式請求が827人となっています。
これは、同年における毀棄・隠匿の罪(起訴総数1,595人のうち公判請求766人、略式請求829人)における公判請求割合67.4%と近い数字です。
このことから、器物損壊罪の実刑・執行猶予の割合も、毀棄・隠匿の罪と大きな差はないと考えられます。
以上を踏まえると、トラブルから他人の物を損壊した場合には、被害額が高額でない限り、通常は不起訴または罰金で処理される可能性が高いといえます。
仮に公判請求されたとしても、前科がある場合や悪質・常習的な犯行でない限り、一般的には執行猶予となる可能性が高いと考えられます。
よくある事例
器物損壊罪でよくある事例は、以下のとおりです。
不起訴とされるケース
器物損壊罪は他人の物を対象とするため、前述のとおり起訴率が低く、不起訴率が高い傾向にあります。この背景には、器物損壊罪が親告罪である点が関係しています。
2024年検察統計年報によれば、不起訴理由の内訳は、不起訴4,493人のうち、起訴猶予1,044人、嫌疑不十分803人、嫌疑なし3人、罪とならず6人、心神喪失16人、親告罪の告訴欠如・無効・取消し2,487人、時効完成114人、その他20人となっています(同年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
告訴の欠如(告訴がそもそもない)、無効(告訴期間経過後の告訴)、取消し(いったんした告訴の撤回)による不起訴は、不起訴全体の55.4%を占めています。
この背景には、被害者との示談や被害弁償が影響していると考えられます。
被害者は、示談あるいは被害弁償があれば、告訴を思いとどまったり(告訴の欠如)、告訴の取消しの可能性があるからです。
器物損壊罪は、他人に物質的損害を与えるものであるため、被害者との示談あるいは被害弁償が、被害者の意識や検察官の処分に影響しているといえます。
弁護士が被害者と交渉するケース
前述のとおり、被害者の告訴がなければ不起訴となり、示談や被害弁償が成立すれば、被害者が告訴を思いとどまったり、告訴を取り消す可能性もあります。
ただし、略式請求となり罰金で終わった場合でも前科が付いてしまうため、可能であれば略式請求も避けたいところです。
では、被害者と示談や被害弁償を進めるにはどうすればよいのでしょうか。
トラブルが原因で物を損壊した場合、加害者本人が直接交渉すると、被害者の心情を害したり、かえって話がこじれる可能性があります。
被害者との交渉は、冷静かつ客観的に対応できる弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士であれば、被害者の心情に配慮しつつ被疑者の反省や謝罪の意を伝え、示談金額を含めて適切に調整してもらえます。
誠意ある謝罪と示談・被害弁償を早期に行うことで、不起訴となる可能性は大きく高まります。
仮に起訴されたとしても、公判請求ではなく略式請求となる可能性が高く、仮に公判請求された場合でも執行猶予となる可能性が高まります。
さらに、実刑が避けられない場合でも、一般的には刑期が軽減される傾向があります。
器物損壊罪にあたらないケース
ビラ貼り行為が器物の美観や効用を害していない場合や、汚損行為であっても汚損の程度が軽く、本来の用途を妨げるほどではない場合には、器物損壊罪における「損壊」には該当せず、器物損壊罪は成立しません。
ただし、これらの行為は軽犯罪法1条33号により、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料で処罰される場合があります。
まとめ
器物損壊罪で逮捕された場合、不安を抱えるのは当然です。早期の釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
器物損壊罪では、被害者との示談や被害弁償が処分結果に大きく影響します。
被害者との交渉や示談の手続きは、法律の専門家である弁護士に任せることが望ましいといえます。
経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについて具体的な助言を得ることができ、被疑者にとって有利な結果につながる可能性が高まります。
器物損壊罪でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。