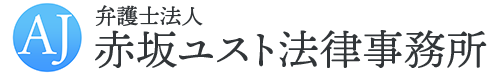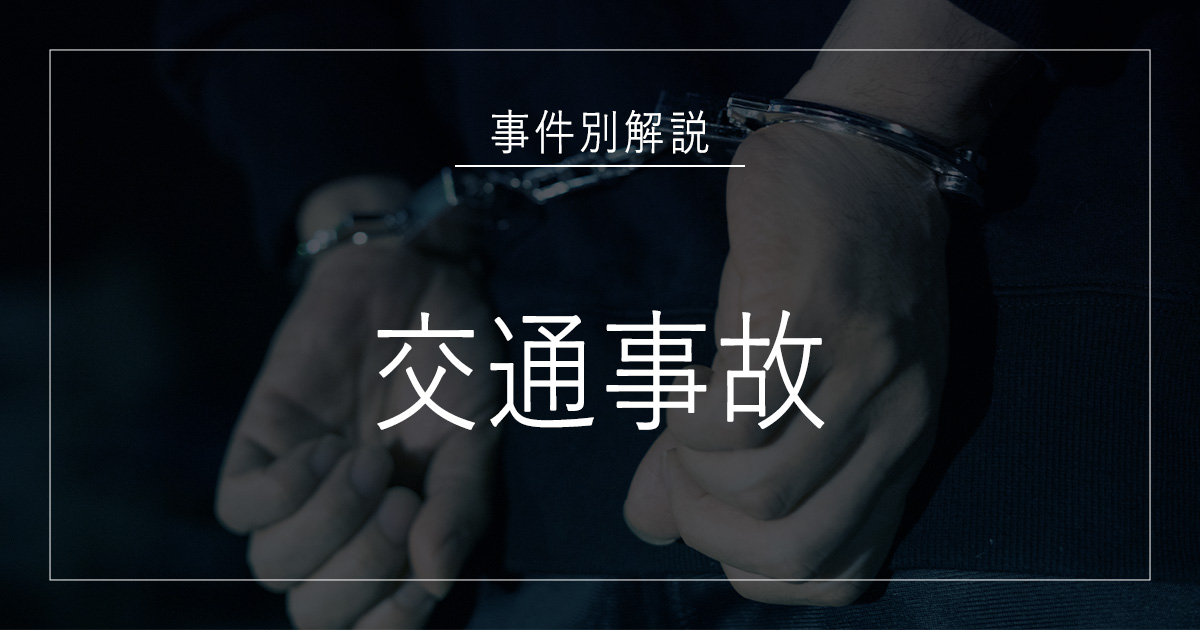突然の交通事故により警察に逮捕されるという状況に直面したとき、多くの方が「このまま長く身体を拘束されるのか」「刑罰はどれほど重いのか」といった不安を抱えます。特に、事故によって人を死傷させてしまった場合、損害賠償にとどまらず、刑事責任も問われることになります。
本記事では、交通事故をめぐる刑事責任の全体像について、適用される法律や各種罪名、法定刑、そして実際に起こり得る典型的な事例に基づいて、わかりやすく解説します。
交通事故と法律の関係
自動車の運転に伴う事故は、職業運転手に限らず、一般市民であっても、わずかな不注意から発生する可能性があります。そのため、交通事故に関する法律は、体系的に整備されています。
なかでも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「法」)は、自動車運転による死傷事故の実情を踏まえ、平成26年(2014年)5月20日に施行されました。
この法律では、悪質性や危険性の高い運転行為に対して、特に厳罰化が図られています。法施行後の改正により、あおり運転などの行為は「危険運転致死傷罪」の対象に追加されました。
また、交通事故の定義については、道路交通法67条2項において、「車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊」とされています。
なお、刑罰における「懲役」および「禁錮」は、令和7年(2025年)6月1日から、それぞれ「拘禁刑」、および「有期拘禁刑」として表記されるようになります(改正刑法施行日より適用)。
交通事故で適用される刑罰の整理
交通事故で適用される罪名や刑罰は、法に基づき体系的に定められています。以下に主な罪名とそれぞれの構成要件、法定刑を紹介します。
危険運転致死傷罪(法2条)
危険運転致死傷罪(法2条)は、故意に一定の悪質で危険な運転行為を行い、その結果、人を死傷させた場合に成立します。
| 人を死傷させる原因となる行為 | 科される刑罰 |
| ①アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で運転(1号) ②自動車の制御が困難な高速度で運転(2号) ③自動車を制御する技能を有しないで運転(3号) ④人や車の通行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近する際、危険な速度で運転(4号) ⑤車の通行を妨害する目的で、危険な速度で走行中の車の前で停止したり、著しく接近するような運転(5号) ⑥高速道路等において、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前で停止したり、著しく接近したりして、走行中の車に停止または徐行させる運転(6号) ⑦赤信号や警察官の手信号などを殊更に無視し、かつ危険な速度で運転(7号) ⑧通行禁止道路を進行し、かつ危険な速度で運転(8号) | (人を負傷させた場合)15年以下の懲役(拘禁刑) (人を死亡させた場合)1年以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| ①アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で運転(1号) ②自動車の制御が困難な高速度で運転(2号) ③自動車を制御する技能を有しないで運転(3号) ④人や車の通行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近する際、危険な速度で運転(4号) ⑤車の通行を妨害する目的で、危険な速度で走行中の車の前で停止したり、著しく接近するような運転(5号) ⑥高速道路等において、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前で停止したり、著しく接近したりして、走行中の車に停止または徐行させる運転(6号) ⑦赤信号や警察官の手信号などを殊更に無視し、かつ危険な速度で運転(7号) ⑧通行禁止道路を進行し、かつ危険な速度で運転(8号) |
| 科される刑罰 |
| (人を負傷させた場合)15年以下の懲役(拘禁刑) (人を死亡させた場合)1年以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
準危険運転致死傷罪(法3条)
準危険運転致死傷罪(法3条)は、アルコールや薬物、または病気の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、アルコールや薬物、または病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥って、人を死傷させた場合に成立します。
| 人を死傷させる原因となる行為 | 科される刑罰 |
| ①アルコールや薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転(1項) ②病気の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転(2項) | (人を負傷させた場合)12年以下の懲役(拘禁刑) (人を死亡させた場合)15年以下の懲役(拘禁刑) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| ①アルコールや薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転(1項) ②病気の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転(2項) |
| 科される刑罰 |
| (人を負傷させた場合)12年以下の懲役(拘禁刑) (人を死亡させた場合)15年以下の懲役(拘禁刑) |
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(法4条)
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、アルコールや薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠って人を死傷させたとき、その運転のときのアルコールや薬物の影響の有無や程度の発覚を免れる目的で、さらにアルコールや薬物を摂取したり、その場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させるなど、その影響の有無や程度の発覚を免れるべき行為をした場合に成立します。
| 罪となる行為 | 科される刑罰 |
| アルコールや薬物の影響の有無や程度の発覚を免れる目的で行う行為 | 12年以下の懲役(拘禁刑) |
| 罪となる行為 |
| アルコールや薬物の影響の有無や程度の発覚を免れる目的で行う行為 |
| 科される刑罰 |
| 12年以下の懲役(拘禁刑) |
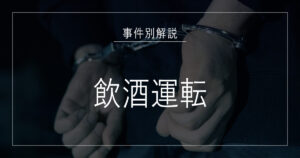
過失運転致死傷罪(法5条)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果、人を死傷させた場合に成立します。
| 人を死傷させる原因となる行為 | 科される刑罰 |
| 前方不注視、わき見、信号見落とし、不適正な速度、ハンドル操作ミス、車間距離不保持、一時不停止、左右の安全不確認など、注意義務に違反する運転 | 7年以下の懲役もしくは禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金(ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑が免除される場合があります) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| 前方不注視、わき見、信号見落とし、不適正な速度、ハンドル操作ミス、車間距離不保持、一時不停止、左右の安全不確認など、注意義務に違反する運転 |
| 科される刑罰 |
| 7年以下の懲役もしくは禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金(ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑が免除される場合があります) |
無免許運転による加重の罪(法6条)
無免許運転による加重の罪は、法2条(3号を除きます)ないし5条の罪を犯したとき、無免許で自動車を運転した場合に成立します。
| 人を死傷させる原因となる行為 | 科される刑罰 |
| 法2条(3号を除きます)の罪を犯し、人を負傷させたとき、無免許で運転 | (人を負傷させた場合のみ)6か月以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 法3条の罪を犯したとき、無免許で運転 | (人を負傷させた場合)15年以下の懲役(拘禁刑) (人を死亡させた場合)6か月以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 法4条の罪を犯したとき、無免許で運転 | 15年以下の懲役(拘禁刑) |
| 法5条の罪を犯したとき、無免許で運転 | 10年以下の懲役(拘禁刑) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| 法2条(3号を除きます)の罪を犯し、人を負傷させたとき、無免許で運転 |
| 科される刑罰 |
| (人を負傷させた場合のみ)6か月以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| 法3条の罪を犯したとき、無免許で運転 |
| 科される刑罰 |
| (人を負傷させた場合)15年以下の懲役(拘禁刑) (人を死亡させた場合)6か月以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| 法4条の罪を犯したとき、無免許で運転 |
| 科される刑罰 |
| 15年以下の懲役(拘禁刑) |
| 人を死傷させる原因となる行為 |
| 法5条の罪を犯したとき、無免許で運転 |
| 科される刑罰 |
| 10年以下の懲役(拘禁刑) |
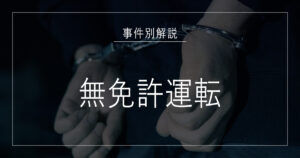
よくある事例
交通事故でよくある事例は、以下のとおりです。
あおり運転のケース
あおり運転(妨害運転)によって交通事故を起こし、その結果人を死傷させれば、危険運転致死傷罪に問われます。
交通事故の原因となるあおり運転は、法2条の4号・5号・6号で定められています。
危険な速度を出しながら、人や車の通行を妨害しようとして、走行中の車の直前に割り込んだり、通行中の人や車に異常に接近したりして、その結果人や車と衝突して人を死傷させれば、あおり運転による危険運転致死傷罪となります(4号の場合)。
相手車両が高速度で走行しているときに、相手車両の走行を妨害しようとして、前方に割り込んで急停車したり、幅寄せしたりして、その結果相手車両と衝突して人を死傷させれば、あおり運転による危険運転致死傷罪となります(5号の場合)。
高速道路や自動車専用道路で、走行中の相手車両の走行を妨害しようとして、前方に割り込んで急停車したり、幅寄せしたりして、相手車両に停止や徐行をさせ、その結果相手車両と衝突して人を死傷させれば、あおり運転による危険運転致死傷罪となります(6号の場合)。
通行禁止道路を運転するケース
「通行禁止道路」を自動車で進行することは、悪質で危険な運転といえるため、危険な速度で運転して交通事故を起こし、その結果人を死傷させれば、危険運転致死傷罪に問われます。
「通行禁止道路」は、政令で定められており、具体的には以下の道路や部分がこれにあたります。
- 車両通行止め道路
- 自転車および歩行者専用道路
- 一方通行道路(の逆走)
- 高速道路の反対車線
- 安全地帯または立ち入り禁止部分(路面電車の電停等)
運転時のアルコールや薬物の発覚を恐れて逃げるケース
アルコールや薬物を摂取した状態で交通事故を起こし、その結果人を死傷させながら、運転時のアルコールや薬物の影響の有無や程度が発覚することを恐れて逃げた場合には、まず、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に問われます。
さらに、人を死傷させてその場から逃げた場合には、ひき逃げの罪も成立し、道路交通法の救護義務違反の罪として、10年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金に処せられます。
その結果、両罪は併合罪の関係となるため、最高で18年の懲役(拘禁刑)に処せられます。
まとめ
交通事故で逮捕された場合、不安や疑問が募ることと思います。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すには、できるだけ早期に弁護士へ相談することが重要です。
交通事故に適用される法律は、厳罰化の流れの中で成立していますので、刑罰が大幅に加重されています。
弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。交通事故でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
法律問題でお悩みの方は
当事務所へご相談ください!
当事務所へ
ご相談ください!