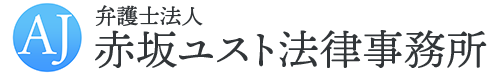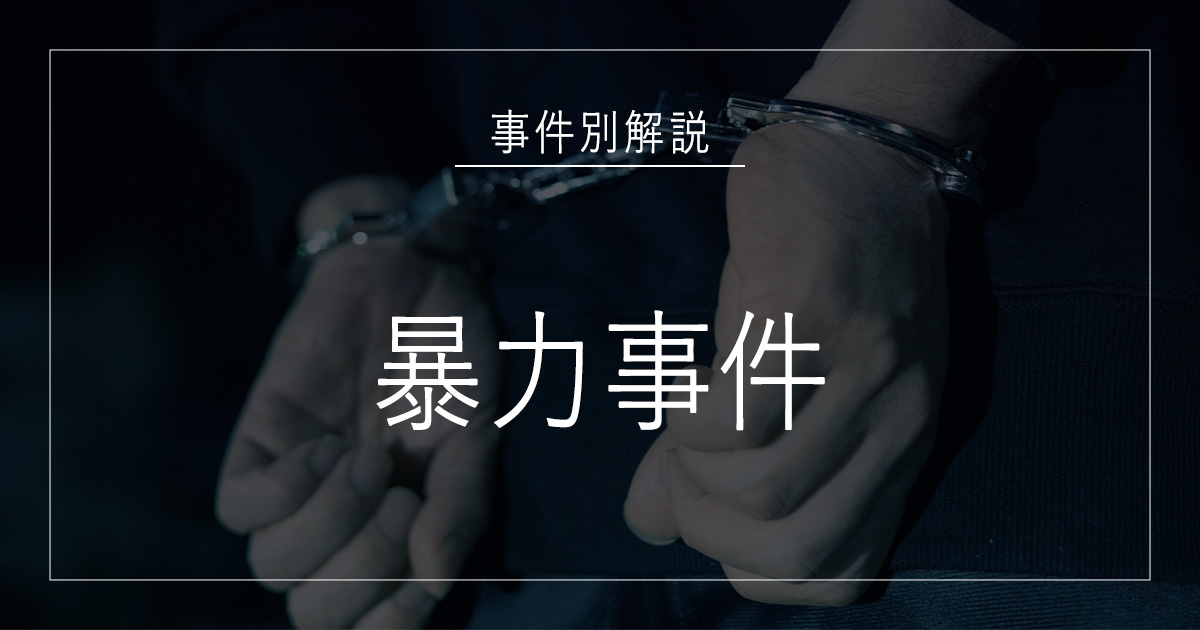暴力事件で逮捕された場合、身柄拘束がどのくらい続くのか、起訴・不起訴の処分はどうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
また、被疑者の家族も、検察官の処分や裁判所の裁判結果が少しでも有利になることを願い、刑事事件に精通した弁護士を頼りたいと望んでいることでしょう。
以下では、暴力事件の身柄状況、暴力事件の終局処理状況、殺人および傷害致死の各罪の判決結果、暴力事件の刑罰、暴力事件の処分状況と判決から見る特色、よくある事例などについて説明します。
暴力事件とは
暴力事件とは、人に何らかの危害を加え、その身体や生命を侵害することを基本とする犯罪です。
暴力事件にはさまざまな態様がありますが、代表的な犯罪類型として、次の罪が挙げられます。
- 公務執行妨害罪
- 殺人罪
- 傷害罪
- 傷害致死罪
- 暴行罪
- 脅迫罪
- 器物損壊罪
なお、本コラムにおいては、刑法上の条文については、単に条文番号のみを掲げるものとします。
暴力事件の身柄状況
以下、暴力事件の身柄状況について説明します。
令和6年版犯罪白書(令和5年の統計)および令和5年検察統計年報(以下、まとめて「犯罪白書等」といいます)によると、令和5年(2023年)の検察庁既済事件における身柄状況(罪名別)は下記の通りです。
| 罪名 | 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 | 警察等で逮捕後釈放 | 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率(%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率(%) | |
| 公務執行妨害 | 1,796 | 234 | 285 | 1,276 | 1 | 71.1 | 890 | 148 | 81.3 |
| 殺人 | 1,098 | 694 | 3 | 400 | 1 | 36.5 | 399 | ― | 99.5 |
| 傷害 | 20,905 | 9,951 | 948 | 9,996 | 10 | 47.9 | 8,767 | 426 | 91.9 |
| 暴行 | 17,263 | 10,352 | 1,277 | 5,627 | 7 | 32.6 | 4,231 | 441 | 82.9 |
| 脅迫 | 2,675 | 1,184 | 38 | 1,453 | ― | 54.3 | 1,359 | 36 | 96.0 |
| 毀棄隠匿 | 7,531 | 4,559 | 371 | 2,597 | 4 | 34.5 | 2,047 | 245 | 88.1 |
公務執行妨害には、刑法第5章(公務の執行を妨害する罪)の公務執行妨害を含むすべての罪を含みます。
殺人には嬰児殺および自殺関与の各罪を、傷害には傷害致死および現場助勢の各罪を含みます。
脅迫には、刑法第32章(脅迫の罪)の強要罪を含みます。
毀棄・隠匿には、刑法第40章(毀棄および隠匿の罪)の器物損壊を含むすべての罪を含みます。
身柄率は (B + C) ÷ A で、勾留請求率は (D + E) ÷ (B + C) でそれぞれ求められます。
暴力事件の終局処理状況
以下、暴力事件の終局処理状況について説明します。
犯罪白書等によると、令和5年(2023年)の検察庁終局処理人員(罪名別)は下記表のとおりです。
| 罪名 | 総数 | 起訴(起訴率) | 公判請求(起訴で占める率) | 略式請求(起訴で占める率) | 不起訴(不起訴率) | 起訴猶予(不起訴で占める率) | その他(不起訴で占める率) |
| 公務執行防害 | 1,602 | 712(44.4%) | 307(43.1%) | 405(56.9%) | 890(55.6%) | 748(84.0%) | 142(16.0%) |
| 殺人 | 931 | 255(27.4%) | 255 | ― | 676(72.6%) | 34(5.0%) | 642(95.0%) |
| 傷害 | 18,449 | 5,688(30.8%) | 1,985(34.9%) | 3,703(65.1%) | 12,761(69.2%) | 9,894(77.5%) | 2,867(22.5%) |
| 傷害致死 | 114 | 83(72.8%) | 83 | ― | 31(27.2%) | 3(9.7%) | 28(90.3%) |
| 暴行 | 16,241 | 4,492(27.7%) | 653(14.5%) | 3,839(85.5%) | 11,749(72.3%) | 10,296(87.6%) | 1,453(12.4%) |
| 脅迫 | 1,931 | 702(36.4%) | 227(32.3%) | 475(67.7%) | 1,229(63.6%) | 907(73.8%) | 322(26.2%) |
| 器物損壊 | 5,951 | 1,343(22.6%) | 516(38.4%) | 827(61.6%) | 4,608(77.4%) | 1,018(22.1%) | 3,590(77.9%) |
起訴率は、起訴人員 ÷ (起訴人員 + 不起訴人員) × 100 の計算式で得た百分比、不起訴率は、不起訴人員 ÷ (起訴人員 + 不起訴人員) × 100 の計算式で得た百分比です。
なお、殺人には殺人予備、嬰児殺および自殺関与の各罪を含みます。
殺人および傷害致死の各罪の判決結果
犯罪白書等によると、裁判員裁判対象事件の第一審における殺人および傷害致死の判決人員(罪名別、裁判内容別)は下記の通りです。
| 罪名 | 総数 | 有罪(実刑) | 執行猶予(有罪の執行猶予率) | 無罪 | |||||||
| 無期 | 20年を超える | 20年以下 | 15年以下 | 10年以下 | 7年以下 | 5年以下 | 3年以下 | ||||
| 殺人 | 196 | 5 | 10 | 26 | 30 | 33 | 22 | 20 | 5 | 41(21.4%) | 4 |
| 傷害致死 | 80 | ― | 1 | ― | 8 | 31 | 13 | 15 | 2 | 9(11.4%) | 1 |
なお、殺人は、自殺関与および同意殺人の各罪を除きます。
暴力事件の刑罰
暴力事件の刑罰は、以下の罪名に対応するとおりです。
なお、刑罰に記載されている懲役は「拘禁刑」、有期懲役は「有期拘禁刑」、無期懲役は「無期拘禁刑」と表記されるようになります。この変更は、令和7年(2025年)6月1日(改正刑法施行日)から適用されます。
| 罪名 | 罰条 | 刑罰 |
| 公務執行妨害 | 95条1項 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
| 殺人 | 199条 | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役(拘禁刑) |
| 傷害 | 204条 | 15年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
| 傷害致死 | 205条 | 3年以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 暴行 | 208条 | 2年以下の懲役(拘禁刑)もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
| 脅迫 | 222条 | 2年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金 |
| 器物損壊 | 261条 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金もしくは科料 |
| 罪名 | 公務執行妨害 |
| 罰条 | 95条1項 |
| 罰則 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
| 罪名 | 殺人 |
| 罰条 | 199条 |
| 罰則 | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役(拘禁刑) |
| 罪名 | 傷害 |
| 罰条 | 204条 |
| 罰則 | 15年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
| 罪名 | 傷害致死 |
| 罰条 | 205条 |
| 罰則 | 3年以上の有期懲役(有期拘禁刑) |
| 罪名 | 暴行 |
| 罰条 | 208条 |
| 罰則 | 2年以下の懲役(拘禁刑)もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
| 罪名 | 脅迫 |
| 罰条 | 222条 |
| 罰則 | 2年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金 |
| 罪名 | 器物損壊 |
| 罰条 | 261条 |
| 罰則 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金もしくは科料 |
暴力事件の処分状況と判決から見る特色
それぞれの暴力事件について、犯罪白書等に基づき、身柄状況、起訴・不起訴の処理状況および判決結果(殺人・傷害致死の各罪)から見た特色は、以下のとおりです。
以下の検討は、暴力事件のみの比較で行っています。
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は、職務を行っている公務員に対して暴行または脅迫を加えることで成立します(95条1項)。
適正に執行されている公務を保護するため、公務執行妨害を行う者に対しては、犯罪白書等の身柄状況から明らかなように、他の罪と比較して逮捕率が高いと言えます。
その厳格な姿勢は、起訴・不起訴の処理状況にも現れており、傷害致死罪を除けば、公務執行妨害罪の起訴率が最も高いことが分かります。
殺人罪
殺人罪は、人を殺すことによって成立します(199条)。
殺人罪の起訴率は、上記で見たとおり、27.4%(255人)と低い状況です。
犯罪白書等(特に令和5年検察統計年報)によると、殺人罪の不起訴人数676人(不起訴率72.6%)の内訳は、次のとおりです。
| 不起訴理由 | 人数 |
| 起訴猶予 | 34人 |
| 嫌疑不十分 | 278人 |
| 嫌疑なし | 188人 |
| 罪とならず | 51人 |
| 心神喪失 | 55人 |
| 時効完成 | 3人 |
このように、殺人罪については、不起訴の理由が多岐にわたり、事件に至る背景には複雑な事情があることがうかがわれます。
傷害罪
傷害罪は、人の身体を傷害することによって成立します(204条)。
犯罪白書等によると、傷害罪は事件数が最も多く、傷害罪に次いで事件数の多い暴行罪との比較で見ると、起訴の公判請求率は暴行罪の2倍以上高くなっています。一方、起訴猶予率は暴行罪よりも低い状況です。
このような状況は、被害者に怪我を負わせていることの表れと思われ、示談の成否や被害感情の緩和が検察官の処分に影響していると考えられます。
傷害致死罪
傷害致死罪は、人の身体を傷害し、よって人を死亡させることによって成立します(205条)。
犯罪白書等によると、他の罪と比較しても、傷害致死罪の起訴率が極めて高く、不起訴率も必然的に圧倒的に低くなっています。
このことは、殺人罪の量刑との違いにも表れており、殺意のない方の傷害致死罪の実刑率が89%と高く、執行猶予率は殺人罪の半分の11%にすぎません。
傷害致死罪が厳罰とされるのは、結果はもちろん、特に行為態様と被害者との関係が重視されるからと考えられます。
暴行罪
暴行罪は、人に暴行を加えることによって成立します(208条)。
暴行罪の事件数は、上述したように、傷害罪に次いで多いものの、起訴の略式請求率は、暴力事件の中で最も高くなっています。
このことは、暴行罪が、被害者に対する傷害に至らない身体的打撃にとどまるうえ、暴行罪の法定刑(刑罰)が、暴力事件の中で一番軽いことも影響していると考えられます。
脅迫罪
脅迫罪は、人に対し、その者のまたはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫することによって成立します(222条)。
脅迫罪は、人の精神的打撃を伴うため、人の身体的打撃を伴う暴行罪とよく比較されます。
脅迫罪は、暴行罪よりも起訴率が高く、しかも起訴の公判請求率が暴行罪より2倍以上高くなっています。
脅迫罪は、個人の意思の自由を侵害するものであるため、そのような被害者の被害感情も、検察官の処分に影響していると考えられます。
器物損壊罪
器物損壊罪は、他人の物を損壊しまたは傷害することによって成立します(261条)。
器物損壊罪は、他人の物を対象とするため、人の身体や意思を対象とする他の罪と比較しても、起訴率が最も低く、必然的に不起訴率が最も高くなっています。
一方で、不起訴の起訴猶予率が、殺人および傷害致死の各罪を除く他の罪と比べても、格段に低い状況になっています。
その理由は、器物損壊罪が親告罪であることと関係しています。
犯罪白書等(特に令和5年検察統計年報)によると、器物損壊罪の不起訴人数4,608人の内訳は、次のとおりです。
| 不起訴理由 | 人数 |
| 起訴猶予 | 1,018人 |
| 嫌疑不十分 | 781人 |
| 嫌疑なし | 8人 |
| 罪とならず | 8人 |
| 心神喪失 | 15人 |
| 告訴の欠如・無効・取消 | 2,655人 |
| 時効完成 | 101人 |
告訴の欠如・無効・取消で不起訴とされた割合は、不起訴全体の57.6%にも上ります。
この要因として、被害者との示談や被害弁償が、検察官の処分に強く影響していると考えられます。
被害者は、示談あるいは被害弁償があれば、告訴を思いとどまったり(告訴の欠如)、告訴の取り消しの可能性があるからです。
器物損壊罪は、他人に物質的損害を与えるものであるため、被害者との示談あるいは被害弁償が、検察官の処分に影響しているといえます。
よくある事例
暴力事件でよくある事例は、以下のとおりです。
器物損壊事件で見られる悪質なケース
下記のような態様の犯行では、一般事件の器物損壊と異なり、逮捕後は引き続き勾留され、起訴は免れないばかりでなく、裁判で科される刑も厳しい傾向にあります。一方で、犯人性が争われるケースもあり、そのような場合には、犯行を裏づける立証が問題になります。
自動販売機やコインランドリーの両替機等を損壊する犯行
金銭を盗み取るため、自動販売機やコインランドリーの両替機等を損壊する犯行が、連続的になされたりします。これらの犯行は、対象物件を破壊することによって目的を遂げようとするもので、損害額も高額になるうえ、その悪質性の度合いは高いとされています。
自動車の車体を傷つけ、車体に塗料を塗布し、タイヤをパンクさせる犯行
これらについては、犯行が繰り返される傾向が強く、しかも、場当たり的、無差別・連続的になされる場合が多いとされています。犯人性が争われる場合には、犯行との結びつきとの関係で、釘、千枚通し、ナイフ、塗料等の道具類の存在のほか、防犯カメラの映像が立証の決め手になる場合があります。
自動車・バイク・自転車に放火する犯行
自動車やバイク、自転車に灯油やガソリンをふりかけ、ライターやマッチで火をつけて対象物件を燃やし、幸い公共の危険が発生しなければ、器物損壊罪のみが成立します。この種の犯行は、連続的になされることもあり、近隣住民や社会一般に与える不安や恐怖には大きなものがあります。そのため、科せられる刑罰も厳しくなることが予想されます。犯人性が争われる場合には、被告人と犯行を結びつける証拠として、防犯カメラや自動車の車載カメラの映像が用いられたりします。
脅迫事件で見られるケース
近隣住民とトラブルになり、その揉め事の過程で相手を脅迫した場合、偶然出会った人といさかいになり、難癖をつけて脅迫した場合、また、思いを寄せる相手に対してストーカー行為に及んだ場合などが、脅迫事件の典型例として挙げられます。
なお、ストーカー行為については、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により、一定の規制が設けられていますが、ストーカー行為の延長線上で脅迫行為に及ぶケースも存在します。
裁判では、保釈の許否が問題となることがあります。脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役(拘禁刑)であり、たとえ常習的に行われた場合であっても、原則として権利保釈の除外事由には該当しません。
そのため、罪状認否で起訴事実を認めた場合には、他に保釈を許さない特別な理由がない限り、裁判所は保釈を認めなければなりません。被告人にとっても、保釈の許否は重大な関心事であるといえます。
殺人・傷害致死の各事件における量刑判断が問題となるケース
裁判員裁判においては、どのようにして量刑判断がなされているのでしょうか。
その量刑判断は、一般論として言えば、量刑を「被告人の犯罪行為に相応しい刑事責任を明らかにすること」と捉える考え方(これを「行為責任の原則」といいます)から、まず、犯罪行為それ自体に関する事実(すなわち犯情)の評価をもとに、その犯罪行為に相応しい刑の大枠を設定します。
そして次に、その大枠の中で、被告人に固有の事情などの一般情状を、刑を調整させる要素として被告人に有利ないし不利に考慮し、量刑の一般的傾向ないし、いわゆる量刑相場を踏まえながら、最終的に刑を決定するという手法がとられています。
殺人・傷害致死の各事件の場合、犯情として主に重視されるポイントは次のとおりです。
- 行為態様
(残虐性、執拗性、危険性など) - 結果
(死亡した被害者の数、殺人未遂の場合には傷害者数や傷害の程度など) - 動機
(怨恨、嬰児殺、児童虐待、介護疲れ、無理心中、心中目的、家族関係、けんか、金銭トラブル、男女関係、DV、保険金目的、憤怒、自己保身・発覚のおそれ、無差別、わいせつ目的、背景なし・不明など) - 凶器の有無・種類
(薬物・毒物、刃物類、ひも・ロープ類、棒状の凶器、銃、自動車、凶器なしなど) - 被害者との関係
(親、子(就学前の子、未成年の子、成年の子)、配偶者(内縁を含む)、その他の親族、交際相手、元配偶者・元交際相手、友人・知人、勤務先関係、関係なし・不明など) - 共犯関係
(単独犯か共犯か、共犯であれば主導的立場か従属的立場か、幇助犯なのかなど) - 計画性
(犯行計画の時期、凶器準備の時期、用意周到性の有無、共犯事件であれば打ち合わせや役割分担の状況など)
まとめ
暴力事件で逮捕された場合、不安や疑問が募ることと思います。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
暴力事件の中には、被害者との示談や被害弁償が、被疑者の処分結果に影響を与える場合もあります。そして、被害者との折衝、示談交渉などは、法律のプロである弁護士に委ねるのが望ましいのです。
弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。暴力事件でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。