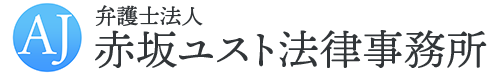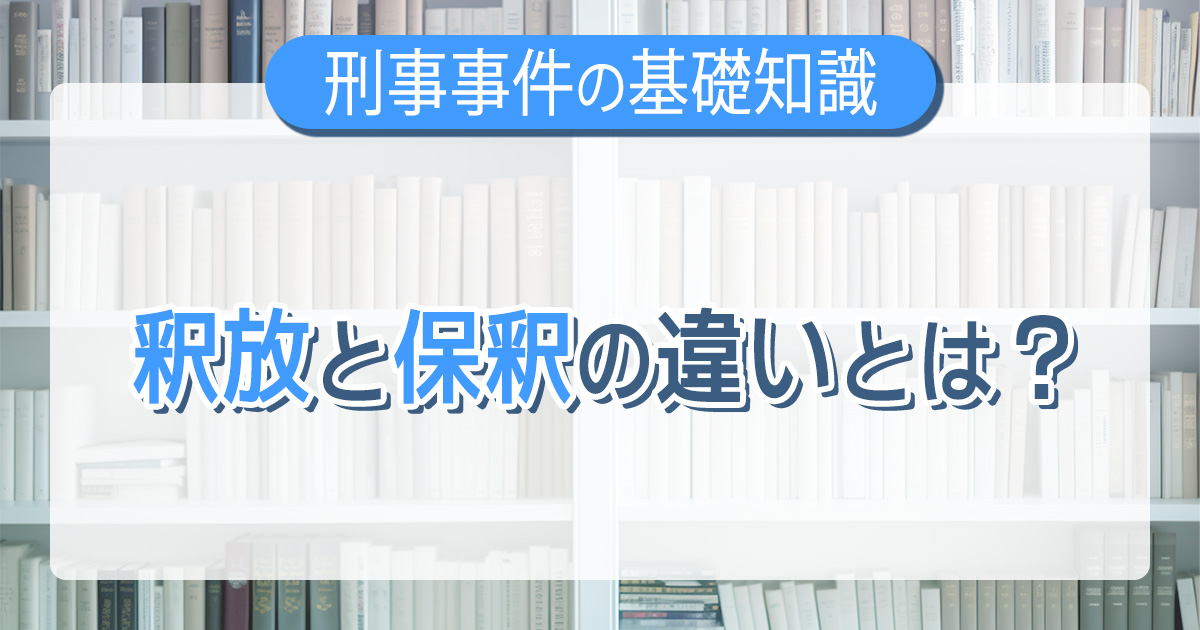刑事事件を起こして逮捕・勾留によって身柄拘束された場合、生活に著しい影響を及ぼします。そのため、身柄の解放が重要となりますが、身柄の解放が認められる場合として釈放と保釈という2つのケースがあります。
以下では、釈放と保釈の違いや、その概要について解説します。
釈放とは
刑事事件において釈放とは、逮捕・勾留されて身柄拘束されている状態から解放されること全般を指す、一般的な用語です。
逮捕・勾留されたとしても、次のような場合には釈放されます。
- 犯罪を行っていない
- 証拠がなく起訴できない
- すでに示談が成立している
- 被害が軽微であるとして不起訴とする場合
- 在宅事件として手続きを進めることになった
- 刑事裁判で無罪・罰金・科料・執行猶予となった
犯罪を行っていない
逮捕・勾留されたものの、実際には犯罪を行っていないと判明すれば、釈放されます。
証拠が無く起訴できない
実際に犯罪を行っていても、証拠が不十分で起訴しても有罪にできない場合は、釈放されます。
不起訴とする場合
実際に犯罪が行われたものの、被害者とすでに示談していたり、被害が軽微であるため不起訴処分とする場合には釈放されます。
在宅事件として手続きを進めることになった
起訴する場合でも逮捕・勾留せずに、被疑者が在宅のまま起訴することもできます。この場合、すでに逮捕・勾留している場合でも釈放されます。
刑事裁判で無罪・罰金・科料・執行猶予となった
起訴されて刑事裁判の結果、無罪・罰金・科料・執行猶予となった場合も、釈放されます。
保釈とは
保釈とは、起訴後の勾留による身体拘束を一時的に解く手続きです。刑事訴訟法で定められており、起訴された被告人やその親族が請求することで行われます。その際、保釈金の納付が必要です。
保釈の要件
保釈は原則として認められますが、以下の場合には認められません。
- 死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪で起訴された
- 前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪で有罪となったことがある
- 常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪で起訴された
- 罪証隠滅を疑う理由がある
- 被害者などの事件の関係者に危害や脅迫などを加えるおそれがある
- 氏名または住居が不明である
保釈が認められない場合に該当しても、諸事情に鑑みて裁判官が許可をすれば保釈ができます。
保釈の手続き
保釈の手続きは、以下の流れで進められます。
- 保釈請求書を裁判官または裁判所に提出する
- 裁判官が検察官に保釈についての意見を求める
- 保釈をするかどうかを決定する(保釈を認める場合には保釈金が決定される)
- 保釈金を納付し釈放される
保釈金は事案によりますが、最低でも100万円程度から、事件の性質や被告人の収入・資産に応じて決まります。保釈金は判決が出れば返還してもらえますが、逃亡・罪証隠滅・関係者を脅迫するなどすると没収されます。
釈放と保釈の違い
釈放と保釈には次のような違いがあります。
| 釈放 | 保釈 | |
| 対象 | すべての人 | 被告人(起訴された人) |
| タイミング | あらゆるタイミング | 起訴された後 |
| 金銭の要否 | 不要 | 保釈金が必要 |
対象
釈放と保釈では対象となる人が異なります。釈放は逮捕・勾留されたすべての人に認められますが、保釈は起訴された被告人にのみ適用されます。
タイミング
釈放と保釈では、認められるタイミングが異なります。釈放は刑事事件のあらゆる段階で行われますが、保釈は起訴後にしか認められません。
金銭の要否
釈放と保釈では金銭の要否が異なります。釈放は捜査機関の判断のみで行われ、金銭を支払う必要はありません。一方で保釈には保釈金の納付が必要です。
釈放・保釈を受けるためには
釈放・保釈を受けるためには、どのような対応が必要でしょうか。
釈放を受けるために行うべきこと
逮捕・勾留は逃亡・罪証隠滅を防止するために行うとされています。そのため、逃亡・罪証隠滅のおそれがないといえる状況を作る必要があります。自首や被害者との示談をすることは逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示すことができるほか、不起訴処分としてもらうために有効です。
保釈を受けるために行うべきこと
保釈についても逃亡・罪証隠滅が行われないと判断してもらえることが重要です。被害者との示談や身元引受人になってもらう人を探すなどが有効です。
まとめ
本記事では釈放と保釈の違いについて解説しました。
どちらも刑事事件で身柄拘束をされているときに身柄を解放してもらうものですが、釈放は身柄を解放してもらうことすべてを指すのに対して、保釈は起訴された後の身柄解放の制度のことを指します。
刑事事件になったときはまずは身柄を解放してもらい、起訴されないようにするのが目標となります。家族が逮捕・勾留などで身柄拘束された場合には、まずは弁護士に相談しましょう。