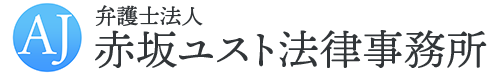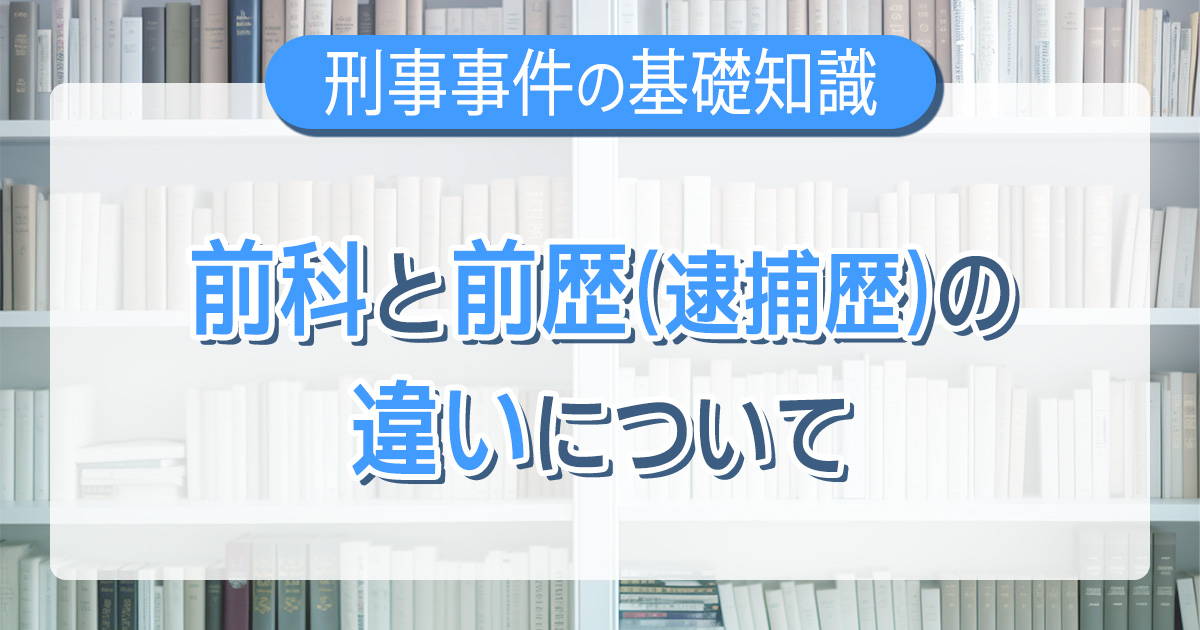犯罪を犯してしまった場合に気になるのが、前科が残ることです。この前科とよく似たものに、前歴(逮捕歴)がありますが、前科と前歴にはどのような違いがあるのでしょうか。
そこで以下では、刑事事件として取り扱われた場合の前科と前歴の違いについて解説します。
前科とは
「前科」とは、過去に有罪とされた経歴のことをいいます。
有罪判決を受けて刑罰を言い渡された場合は、すべて前科になります。これは、懲役や禁錮といった重い刑罰だけでなく、罰金・拘留・科料といった比較的軽い刑罰や、執行猶予付きの判決も含まれます。また、執行猶予期間が経過して刑の言い渡しの効力がなくなった場合でも、有罪判決を受けた事実は消えず、前科として残ります。
一方で、行政から科される過料や反則金、少年事件での保護処分は刑罰ではないため、前科にはなりません。
なお、よく「逮捕されると前科がつく」と誤解されることがありますが、逮捕されても必ず起訴されるとは限りません。また、起訴された場合でも、無罪になる可能性もあります。このような場合は有罪にはならないため、前科はつきません。
前歴とは
「前歴」とは、捜査機関に犯罪の容疑をかけられ、捜査の対象になった経歴のことをいいます。
捜査の対象となったすべての場合が記録され、不起訴となって前科がつかなかった場合でも前歴は残っています。また、逮捕に至らず警察署で事情聴取を受けたり、厳重注意を受けた場合でも、捜査の対象となっているので前歴として残ることになります。
前科と前歴の違い
前科と前歴の違いとして次の点が挙げられます。
- 前科調書への記録
- 勤務先からの懲戒処分
- 一定の資格制限
- 公民権の制限
- 犯罪人名簿への登録
- 再犯加重
- 履歴書への記録
- 海外渡航 など
前科調書が作成される
前科調書とは、過去に有罪判決を受けた者の犯罪歴を記録した書類です。
前科調書は検察庁で管理されており、検察官・検察事務官のみが閲覧できます。記録の対象となるのはすべての前科で、記録が削除されることはありません。起訴されず前歴にとどまる場合には前科調書は作成されません。
勤務先からの懲戒処分
犯罪を犯した場合、勤務先の就業規則により、懲戒処分を受ける可能性があります。特に前科がついた場合、その内容は重大と判断され、解雇や、公務員であれば懲戒免職といった厳しい処分の対象になることがあります。
たとえば、会社からの窃盗のように、会社が被害者となるケースや、会社の評判を著しく損なう行為をした場合は、懲戒処分の対象となる可能性が高くなります。一方で、そうした行為がなく、起訴もされずに前歴だけが残る場合には、懲戒処分の対象とならないこともあります。
一定の資格制限
たとえば、宅地建物取引業法第18条第6項では禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わって5年間を経過していない場合、宅地建物取引士としての登録ができないとされています。その他多くの法律で資格制限が定められています。起訴されず前歴が残っているだけの場合は資格制限がされません。
公民権の制限
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの間など、公民権が制限されることがあります。選挙権・被選挙権・公務員になる権利などの総称が公民権で、公職選挙法や国家公務員法により制限が加えられます。前歴が残っているだけの場合は、公民権の制限はありません。
罰金刑以上の前科は市区町村の犯罪人名簿に記録される
罰金刑以上の前科は市区町村の犯罪人名簿に記録されます。資格制限のある資格の登録をする際に、犯罪人名簿への照会が行われ、資格制限の規定にかからないか調査が行われます。起訴されず前歴が残っているだけの場合は、犯罪人名簿に記録されることはありません。
再犯加重
懲役刑を受けた後、執行終了日または執行免除の日から5年以内に、再び罪を犯して有期懲役に処せられた場合は、再犯とみなされ、再犯加重という不利益を受けます。一方、前歴があるだけの場合は、再犯加重の対象にはなりません。
ただし、再度犯罪を犯した際には、前歴があることが逮捕や拘留の必要性、起訴の判断に影響を及ぼす可能性があります。
履歴書への記載
就職する際に前科がある場合には、履歴書に記載することが求められます。一方で前歴が残っているだけの場合は、履歴書に記載する必要はありません。
海外渡航
海外渡航をする場合に前科があると、入国審査で犯罪経歴証明書やビザの提出を求められることがあり、ケースによっては入国できない可能性もあります。前歴が残っているだけの場合は、海外での入国審査に影響は及びません。
なお、刑の猶予期間が経過した場合や、刑の執行が終わった、または執行の免除を得て一定期間が経過すると、刑の言い渡しの効力が消滅します。この場合、犯罪経歴証明書において前科が記載されないので、海外渡航に影響を及ぼさなくなります。
前科がつかない対策
前科がついてしまうと、就職・資格・海外渡航など、さまざまな場面で不利益を受ける可能性があります。そのため、犯罪を犯してしまった場合には、前科がつかないよう対策を講じる必要があります。
犯罪を犯した場合でも、以下の要素を考慮して不起訴となり、前科がつかない可能性があります。
- 犯人の性格・年齢および境遇
犯罪を犯した経緯や、本人の性格、年齢、家庭環境などが考慮されます。 - 犯罪の軽重および情状
犯罪の内容が軽い場合や、情状酌量の余地がある場合は、不起訴となる可能性があります。 - 犯罪後の情況
被害者への謝罪や被害回復、反省の態度など、犯罪後の対応も重要です。 - 示談の成立
被害者と示談が成立すると、不起訴となる可能性が高まります。そのためには、示談交渉を行い、誠意を示すことが重要です。
これらの対策を適切に行うためには、法律の専門知識が必要となることが多いため、示談交渉や不起訴処分に向けた対応については、弁護士に依頼することを検討しましょう。
まとめ
本記事では、前科と前歴の違いについて解説しました。
前科がつくと、会社を解雇されたり再就職が難しくなり、生活に多大な影響を及ぼします。不起訴処分となれば前歴は残りますが、前科はつきません。不起訴に向けた適切な行動を取るためにも弁護士に相談してください。