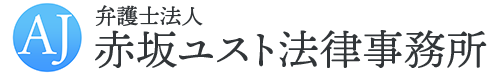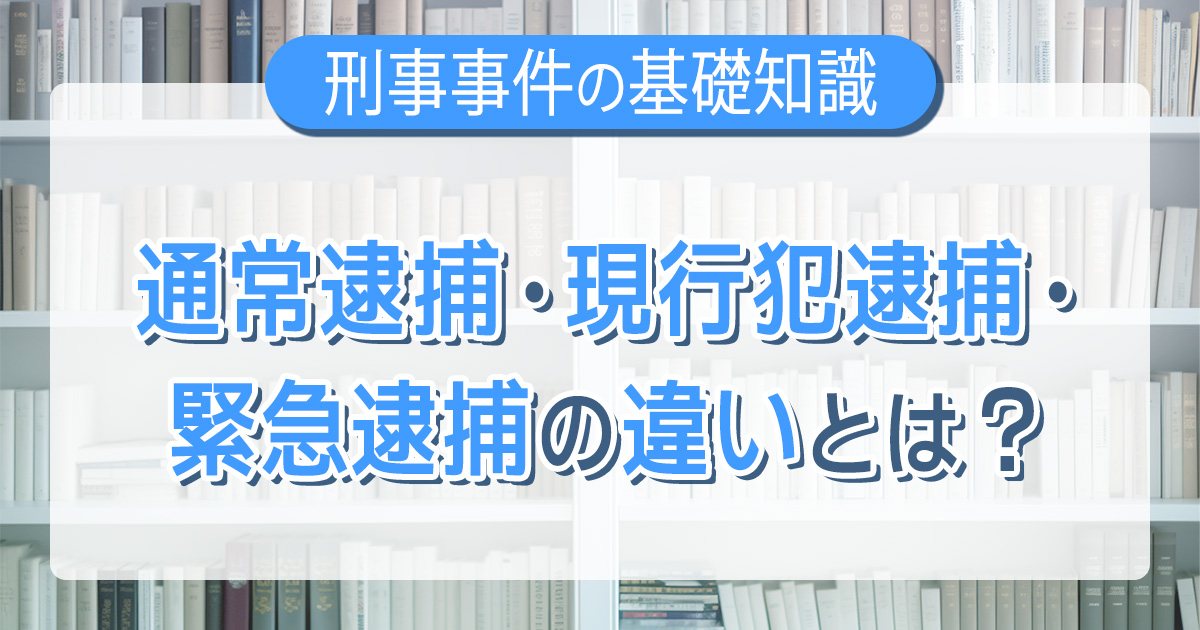犯罪を犯した者の身柄を拘束する「逮捕」には、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3つの種類があります。容疑をかけられた本人や家族は、どのような対応を取ればよいのでしょうか。
そこで以下では、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の違いと、その対応方法について解説します。
逮捕とは
逮捕とは、捜査機関などが被疑者の逃亡および罪証隠滅を防止するため、強制的に身柄を拘束する行為をいいます。
身柄を強制的に拘束するという強い人権侵害を伴う行為です。そのため、憲法第33条で現行犯逮捕以外は、裁判官が発する令状によらなければ逮捕できないとして、厳格な手続きを要求しています。逮捕の種類は次の3つです。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
通常逮捕
通常逮捕とは、裁判官が発する令状(逮捕状)に基づいて行う逮捕です。
憲法第33条の規定を受けて刑事訴訟法第198条で規定されています。
通常逮捕するための要件は次の通りです。
- 検察官・検察事務官・司法警察職員が行う
- 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
- 裁判官があらかじめ発する逮捕状
- 30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪については次のいずれかの要件が必要
- 被疑者が定まった住居を有しない場合
- 正当な理由なく出頭の求めに応じない場合
なお、逮捕状が請求された場合でも、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがなく、明らかに逮捕の必要がないと判断されるときは、逮捕状の請求を却下しなければならないとされています(刑事訴訟規則第143条の3)。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終えた者を逮捕することをいいます。
憲法が逮捕に令状を要求しているのは、捜査を慎重に行うためであり、現行犯については犯罪が行われたことが明白であるため、令状なしでも逮捕を認めています。
現行犯逮捕するための要件は次の通りです。
- 誰でも逮捕できる(警察・検察以外でも可能)
- 現行犯人である、現に罪を行い・行い終わった者
- 刑事訴訟法第212条第2項の規定に該当する(準現行犯逮捕)犯人として追いかけられている
- 盗んだものや、犯罪に使った凶器などを所持している
- 体や服に犯罪の跡がある
- 何かを聞かれて逃走しようとする
現行犯逮捕の場合、事前・事後いずれも逮捕状は不要です。なお、誰でも逮捕して良いのですが、捜査機関以外の人が逮捕した場合には直ちに検察・警察に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法第214条)。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、裁判官の逮捕状を求めることができないほど急を要するときに行う逮捕です。
刑事訴訟法第210条に規定されており、認められる要件は次の通りです。
- 検察官・検察事務官・司法警察職員が行う
- 死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合
- 裁判官の逮捕状を求めることができないほど急を要する
緊急逮捕をした場合には直ちに裁判官の逮捕状を請求し、裁判官が発付しなかった場合は、釈放しなければなりません。
通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の違い
通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕はそれぞれ次のような違いがあります。
| 通常逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
| 逮捕するのは | 検察官、検察事務官、司法警察職員 | 誰でも可 | 検察官、検察事務官、司法警察職員 |
| 逮捕状の要否 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 犯罪の内容 | 限定されない | 限定されない | 死刑・無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪 |
| 通常逮捕 | |
| 逮捕するのは | 検察官、検察事務官、司法警察職員 |
| 逮捕状の要否 | 必要 |
| 犯罪の内容 | 限定されない |
| 現行犯逮捕 | |
| 逮捕するのは | 誰でも可 |
| 逮捕状の要否 | 不要 |
| 犯罪の内容 | 限定されない |
| 緊急逮捕 | |
| 逮捕するのは | 検察官、検察事務官、司法警察職員 |
| 逮捕状の要否 | 必要 |
| 犯罪の内容 | 死刑・無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪 |
現行犯逮捕は警察・検察だけではなく誰でも可能で、逮捕状も不要なのが他の逮捕と違います。緊急逮捕は死刑・無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に限られるのが他の逮捕との違いです。
逮捕された場合の対応
逮捕された場合、どのような対応が必要でしょうか。
目標は早期の身柄解放と不起訴処分
逮捕された場合の目標は、早期の身柄解放と不起訴処分を目指すことです。逮捕後は、72時間以内に引き続き身柄拘束が必要と判断されると、勾留されます。勾留期間は起訴まで最大23日間で、起訴された場合は原則として裁判が終わるまで身柄拘束が続きます。
身柄拘束が続くと、会社や学校に通えなくなり、逮捕された事実が周囲に知られることで、社会的信用を失うおそれがあります。そのため、まずは早期の釈放を目指すことが重要です。さらに、不起訴処分を得て、刑罰が科されて前科がつくのを防ぐことが、逮捕後の基本的な対応となります。
弁護士に依頼して被害者と示談する
逮捕後の身柄解放や不起訴処分を目指すうえで重要なのが、被害者との示談です。示談が成立すれば、罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断され、釈放される可能性があります。また、十分な反省が認められれば、不起訴処分となる可能性も高まります。
ただし、逮捕されている間は、被害者と直接連絡を取ることはできません。そのため、弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を進めてもらう必要があります。
まとめ
本記事では、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の違いと、逮捕された後の対応について解説しました。逮捕には3つの種類があり、誰が逮捕できるか、令状が必要かどうか、対象となる犯罪などに違いがあります。
逮捕された場合は、釈放や不起訴処分を目指して、被害者との示談などの対応を進めることが重要です。そのためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。