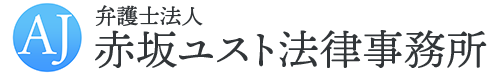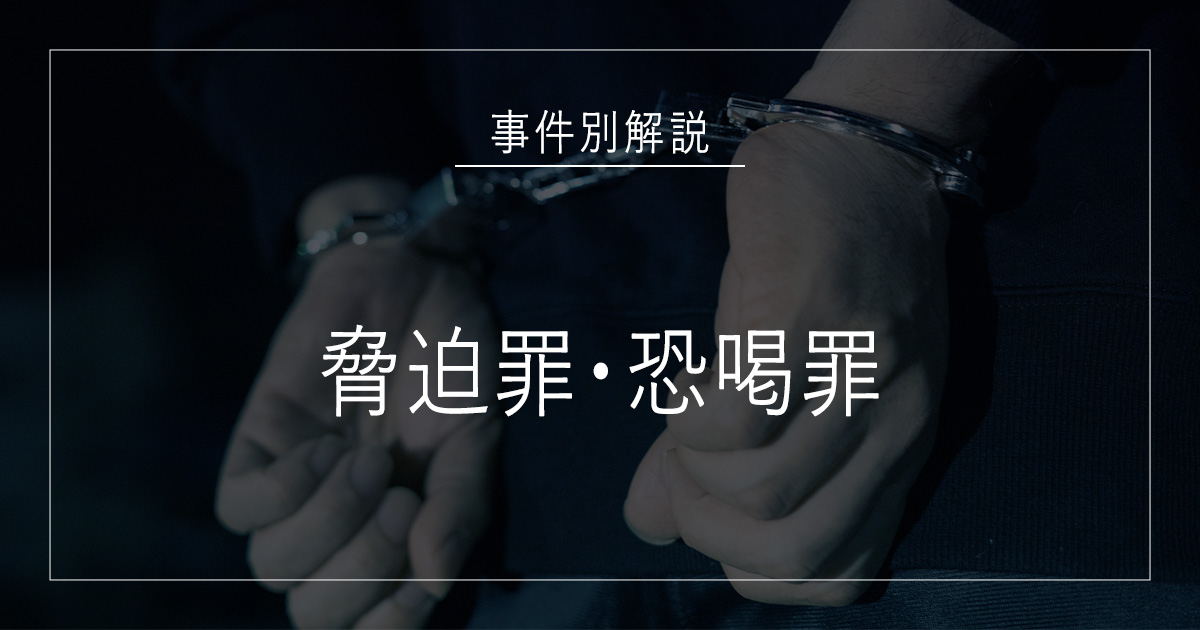脅迫罪や恐喝罪で逮捕された場合、このまま身柄拘束が続くのか、起訴・不起訴の判断がどうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者の家族も、検察官の処分や裁判結果が少しでも有利になることを願い、刑事事件に精通した弁護士に依頼したいと考えることが多いでしょう。
しかし、脅迫罪や恐喝罪は、相手を脅して畏怖させる態様の犯罪であり、決して軽い罪ではありません。
以下では、脅迫罪と恐喝罪の内容、脅迫罪と恐喝罪の身柄状況、脅迫罪・恐喝罪で逮捕された後はどうなるのか、脅迫罪と恐喝罪の終局処理状況、実務上問題となる事例などについて説明します。
なお、以下の刑法における条文は、単に条文番号のみを掲げています。
脅迫罪と恐喝罪の内容
以下で、脅迫罪と恐喝罪の内容について見てみましょう。
脅迫罪の内容
犯罪の成立
脅迫罪は、人に対し、その者(1項)またはその親族(2項)の生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知して脅迫することで成立します(222条)。
客体
客体は人であり、自然人に限られると解されています。
行為
行為は、人を脅迫することです。ここでいう「脅迫」とは、人を畏怖させる程度の害悪を告知する行為を指します。
害悪の告知には、相手を畏怖させるために次のような言動が用いられることがあります。
- 「命で償ってもらう」:生命への加害を示すもの
- 「殴ってやろうか」:身体への加害を示すもの
- 「コンテナに入ってもらうぞ」:自由を奪うことを示すもの
- 「奥さんが不倫していることをばらすぞ」:名誉を害することを示すもの
- 「火の元に気をつけたらどうだ」:財産への危険を暗示するもの
告知される害悪は、通常人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、その判断は告知内容や周囲の客観的状況によって行われます(判例)。
告知の方法に制限はなく、直接口頭で告げるほか、SNS・書面・パソコンで送付する方法や、挙動によって加害を暗示する方法でも構いません。
刑罰
脅迫罪の法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(222条)。なお、脅迫罪の未遂は処罰されません。
恐喝罪の内容
犯罪の成立
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させること(1項)、または財産上不法の利益を得る、もしくは他人に得させること(2項)によって成立します(249条)。
客体
客体は、1項では他人の財物、2項では財産上の利益です。
行為
行為は、前述したとおり、1項および2項に定められた行為内容に該当します。
恐喝とは、財物または財産上の利益を得る手段として相手を脅迫または暴行することをいいます。
恐喝罪は、脅迫・暴行が反抗を抑圧する程度に至らない点で、強盗罪と区別されます。
人を畏怖させる害悪の告知は、脅迫罪とは異なり、生命・身体・自由・名誉・財産に限られる必要はありません。
相手本人や親族以外の者、たとえば友人や知人に関する内容であっても該当します。
「財物を交付させる」とは、畏怖した被害者が財産的処分行為を行い、行為者が財物の占有を取得することをいいます。
「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」とは、不法に財産上の利益を得、または得させることであって、財産上の利益そのものが不法である必要はありません。
すなわち、相手を恐喝して畏怖させた結果、その相手の財産的処分行為によって、行為者または行為者と一定の関係にある第三者が、財産上の利益を取得することをいいます。
「財産上不法の利益」には、次のような利益が含まれます。
- 債務の免除
- 支払猶予
- 履行期の延期
- 債務を負担する約束
- 労務の提供(自動車の運転や輸送サービスなど)
刑罰
恐喝罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です(249条)。また、恐喝罪の未遂も処罰されます(250条)。
脅迫罪と恐喝罪の身柄状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年における検察庁既済事件の身柄状況(脅迫罪と恐喝罪)は下記のとおりです(同年報「41 罪名別・既済となった事件の被疑者の逮捕および逮捕後の措置別人員」参照)。
| 罪名 | 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 | 警察等で逮捕後釈放 | 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率(%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率(%) | |
| 脅迫 | 2,595 | 1,214 | 34 | 1,346 | 1 | 51.9 | 1,251 | 43 | 96.1 |
| 恐喝 | 2,038 | 544 | 6 | 1,488 | 0 | 73.0 | 1,445 | 9 | 97.7 |
| 罪名 | 脅迫 | 恐喝 | |
| 逮捕関係 | 総数(A) | 2,595 | 2,038 |
| 逮捕されない者 | 1,214 | 544 | |
| 警察等で逮捕後釈放 | 34 | 6 | |
| 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 1,346 | 1,488 | |
| 検察庁で逮捕(C) | 1 | 0 | |
| 身柄率(%) | 51.9 | 73.0 | |
| 勾留関係 | 認容(D) | 1,251 | 1,445 |
| 却下(E) | 43 | 9 | |
| 勾留請求率(%) | 96.1 | 97.7 | |
身柄率は(B+C)÷Aで、勾留請求率は(D+E)÷(B+C)でそれぞれ求めます。
上記の数字から、脅迫罪では53.2%が逮捕され、46.8%は逮捕されていないことになります。また、恐喝罪では73.3%が逮捕され、26.7%が逮捕されていません。
脅迫罪・恐喝罪で逮捕された後はどうなるのか
前述の身柄状況によれば、脅迫罪で逮捕された場合の勾留請求率は96.1%、勾留認容率は96.7%です。また、恐喝罪では勾留請求率97.7%、勾留認容率99.4%となっています。
したがって、脅迫罪や恐喝罪で逮捕された被疑者の多くは、その後も勾留されることになります。
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内の勾留延長を認めることがあります。
延長が認められるのは、捜査を継続しなければ処分できない場合、10日間で捜査を尽くせなかった場合、延長により捜査の障害が解消される場合など、複数の事由がそろっているときです。
脅迫罪と恐喝罪の終局処理状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年の脅迫罪と恐喝罪の検察庁終局処理人員は下記表のとおりです(同年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
| 罪名 | 総数 | 起訴 (起訴率) | 公判請求 (起訴で占める率) | 略式請求 (起訴で占める率) | 不起訴 (不起訴率) | 起訴猶予 (不起訴で占める率) | その他 (不起訴で占める率) |
| 脅迫 | 1,874 | 703 (37.5%) | 232 (33.0%) | 471 (67.0%) | 1,171 (62.5%) | 876 (74.8%) | 295 (25.2%) |
| 恐喝 | 1,497 | 397 (26.5%) | 397 | ― | 1,100 (73.5%) | 501 (45.5%) | 599 (54.5%) |
| 罪名 | 脅迫 | 恐喝 |
| 総数 | 1,874 | 1,497 |
| 起訴 (起訴率) | 703 (37.5%) | 397 (26.5%) |
| 公判請求 (起訴で占める率) | 232 (33.0%) | 397 |
| 略式請求 (起訴で占める率) | 471 (67.0%) | ― |
| 不起訴 (不起訴率) | 1,171 (62.5%) | 1,100 (73.5%) |
| 起訴猶予 (不起訴で占める率) | 876 (74.8%) | 501 (45.5%) |
| その他 (不起訴で占める率) | 295 (25.2%) | 599 (54.5%) |
起訴率は、「起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100 で算出される割合をいいます。
不起訴率も同様で、「不起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100 により求められる割合です。
上記の数字から、脅迫罪・恐喝罪いずれも起訴率より不起訴率の方が高く、不起訴の中でも起訴猶予が占める割合が大きいことが分かります。
不起訴率が高い背景としては、被害者との示談、被害弁償(恐喝の場合)、慰謝の措置が大きな要因であると考えられます。
実務上問題となる事例
実務上、脅迫罪や恐喝罪で問題となる事例には、次のようなものがあります。
脅迫罪で逮捕されやすいケース
脅迫罪で逮捕されやすいケースは、以下のような場合です。
①SNSに害悪の告知が残っている、脅迫内容の書面に指紋が付着している、パソコン内に告知データが保存されているなど、容疑者の関与を示す客観的証拠があるにもかかわらず、容疑者が関与を否定している場合は、逮捕される可能性が高くなります。
②被害者が元妻や元交際相手である場合、ストーカー規制法による規制が及ぶだけでなく、脅迫が傷害や殺人などの重大な犯罪に発展するおそれもあるため、逮捕される可能性が高くなります。
➂容疑者が暴力団やいわゆる半グレなどの反社会的勢力と関係している場合、被害者への働きかけによる罪証隠滅のおそれが高く、逃亡のおそれも強いため、逮捕されるのが原則といえます。
脅迫罪における処分状況
脅迫罪のみの科刑状況の統計はありませんが、送致後の起訴・不起訴の割合、公判請求と略式請求の割合、不起訴に占める起訴猶予の割合などから判断すると、処分判断に最も影響する要素は被害者との示談や慰謝の措置であると考えられます。
被害者に対して誠意ある謝罪を行い、示談や慰謝の措置を適切に進めることができれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
仮に起訴された場合でも、略式請求となる可能性があり、罰金では処理できず公判請求となったとしても、執行猶予付き判決が選択される可能性が高くなります。
また、法律上実刑が避けられないケースであっても、一般的には刑期が軽減される傾向があります。
恐喝罪における科刑状況
令和6年版犯罪白書(令和5年の統計)によれば、地方裁判所における恐喝罪の科刑状況は、下記表のとおりです(同白書「資料2-3地方裁判所における死刑・懲役・禁錮の科刑状況(罪名別)」参照)。
| 総数 | 実刑 (実刑率)74 (29.6%)(実刑で占める率) | 執行猶予(執行猶予率) | ||||
| 250 | 5年を超え7年以下 | 3年を超え5年以下 | 2年以上3年以下 | 1年以上2年未満 | 6か月以上1年未満 | 176(70.4%) |
| 人数 | 1(1.3%) | 13(17.6%) | 38(51.4%) | 21(28.4%) | 1(1.3%) | |
上記の数字によれば、恐喝罪で起訴された場合、実刑率は3割弱(数字上は29.6%)、執行猶予率は7割強(数字上は70.4%)です。
そのため、特段の前科がなく、被害者と示談したり、被害弁償や慰謝の措置を講じたりすれば、執行猶予が付く可能性が高いといえます。
ただし、次のような犯行については犯情が悪く、被害者の被害感情も強いため、判決結果(実刑や刑期)に厳しく反映される傾向があります。
- いわゆる「かつあげ」
- 暴力団員による犯行
- 企業を対象とした大胆な犯行
- 個人の秘密や不利益な情報を材料(いわゆる「ねた」)として脅す卑劣な犯行
まとめ
脅迫罪や恐喝罪で有利な結果を得るためには、被害者との示談、被害弁償(恐喝の場合)、慰謝の措置が大きな要素を占めると考えられます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、被害者との示談交渉を丁寧に進め、被害者の宥恕(許し)が得られた場合には、不起訴処分や罰金(脅迫罪の場合)といった有利な結果につながる可能性があります。
さらに、公判請求された場合でも執行猶予付き判決となる可能性が高く、仮に実刑となっても刑期が軽減される可能性があります。
脅迫罪や恐喝罪でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。